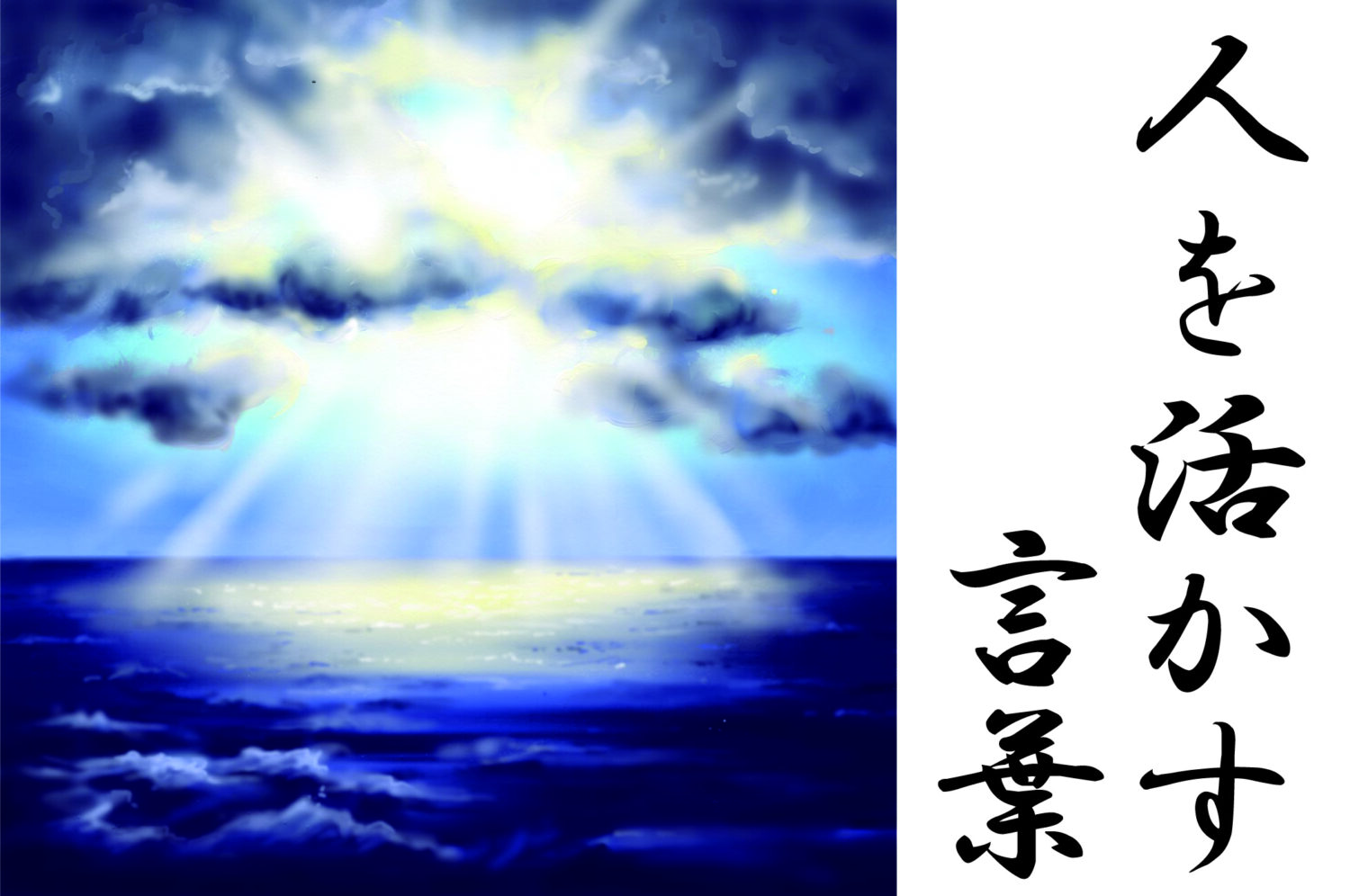少年と怪物
四月
不思議なふたり
【一九八八年 七月二十日 十時十分 網船小学校 相原江利】
初恋。
だれにとっても長く噛みしめられる最上の思い出―それが江利にやってきたのはこの日、この時だった。
あの細い目と癖のある髪、なにより彼がしたことに、胸の奥をつかまれた。
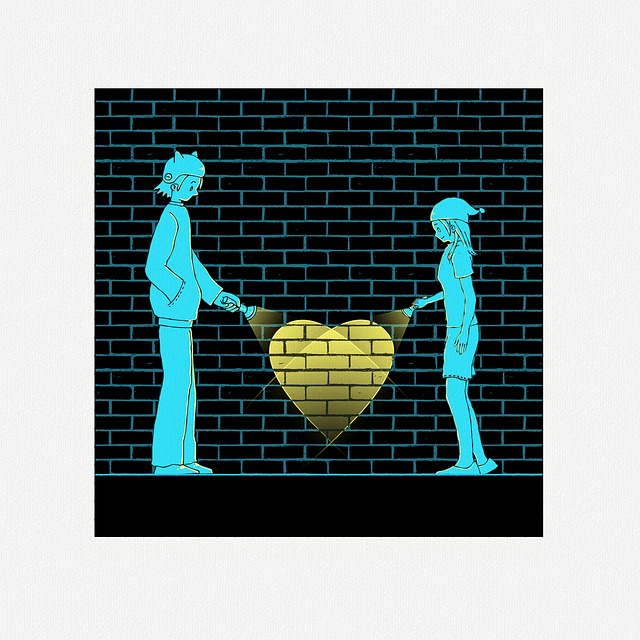
海漁町にはぜんぶで四つの小学校がある。
江利のかよう網船小学校は、町のもっとも南―千葉県のほぼ最南端にあった。
内房線の海漁町駅からも一番離れていて(歩けば一時間ほどかかる)、奥名山のふもとからすこし離れた田畑と少々の家の中に、ひとつだけ場違いに大きく、でんと建っている。
上空から見れば校舎はFの形をしている。
上の長い横棒が五年生と六年生の木造校舎、
下の短い横棒が一年生から四年生の木造校舎、
これらはどちらも平屋で、妖怪に化けて子どもたちを食べてしまいそうなほど古い。
縦棒が職員室や理科室、音楽室、家庭科室や保健室などのある教職員棟で、児童たちからは本校舎と呼ばれている。コンクリートの二階建てである。
Fの足が体育館であり、腹の部分の空白は校庭やプール、滑り台やブランコや砂場、アスレチックなどがある。

二時間目の国語の授業が終わった二十分の休み時間、江利は木造校舎から本校舎への渡り廊下にいた。
うつむきながら簀の子を踏んでいった。
百八十人の児童が一斉に遊ぶ声が、外の運動場から聞こえてくる。
二十年もしない後の世は、八月のひと月で三十度を超える日が二十八日を数えてもめずらしくもなんともない気候異常になるが、
一九八八年のこの日は気温二十九・五度。
この時代からすればめずらしい暑さだった。
(温暖化などという言葉はまだなかった)

「あっちい」
江利はいらだちながら言った。
そうして『もっと女の子らしい言葉遣いをしなさい』という母親の小言を思い出し、
「クソあっちい」と言った。
千葉のド田舎の学校に冷房器具など無い。
東京で通っていた私立の幼稚園が懐かしかった。
あとわずか二日だが、早く夏休みにならないかと思う。
手の甲にまで汗をかいて、江利は赤いスカートのすそで乱暴にでぬぐった。
足下の簀の子は合板ではなく、本物の木で、弾力があり、踏むたびに沈んで、耳ざわりにきしんだ。
雨がしみ、黒ずんだ年輪は乾いた血のように見えた。
江利は、音が大きく鳴りそうな場所をド、レ、ミ、ファと口ずさみながらリズミカルに踏んで、本校舎に入った。

本校舎は鉄筋造りで、大きな鉄の箱のようだった。
窓が少なく、いつも薄暗い。
厚いコンクリートが外の日差しを防ぐので、空気はひやりとしていた。
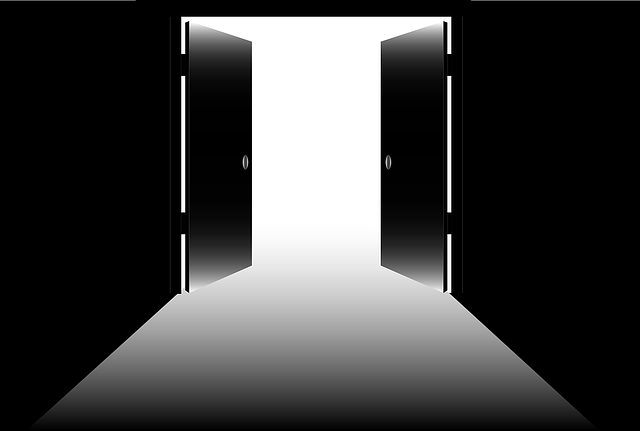
「なんだそのツラは! 腐れドチビが! ぶっとばされてえか!」
前方から突然きこえた大きな声で、江利は顔をあげた。
白い壁と灰色のタイルの先、T字路の真ん中で、何人か、男の子たちが向かいあっている。
背の大きいほうが四人、小さいほうは二人だった。
(けんか)
江利は思った。
そして、
(けんかじゃない。いじめだわ)
と、すぐに思い直した。
大きい四人は六年生だった。
六年生といえば小学校においては地獄の鬼とおなじだ。
たぶんあの六年生たちのだれかに、今日はなにかとても気にいらないこと、
たとえば宿題を忘れて先生にげんこつをくらったとか、
犬のうんこを踏んづけて友達にからかわれたとか、
そういうことがあって、目についた小さな子をいじめているのだ。
乱暴なことで有名な四人組だった。
かれらの口からは下級生を泣かすような悪口しかでない。
その手は、鼻くそをほじって下級生の頭になすりつけるか、殴るか、どちらかしかできない。
かれらがにらめば、少年ジャンプは破れ、ファミコンのソフトは消えた。
かれらの蹴ったサッカーボールは、かならずだれかの頭を直撃する。
かれらが浜通りの駄菓子屋―浜駄菓のまえにいれば、不思議な力でだれかがつまづき、ポケットの小銭をバラまいてしまう。エスパー魔美みたいな力を持っているのだ。
もちろん、かれらは親切に拾ってくれる。だがお礼は、拾ったお金の全部だ。

いつだったか江利も、あのうちの一人に、おさげをいやというほど引っ張られたことがった。
泣きはしなかったが、
「おい、気どり屋のよそもん」と、怒鳴られたことを思いだし、江利は立ちすくんでしまった。
(引っ越してきたのは三年も前のことなのに、この田舎では、だれもそれを忘れてくれない)
「チンカスやろう! ナメてんのか? あん?」
坊主頭で、黄色と黒の縞のシャツを着て、すごく体格のいい六年が怒鳴った。
ちょっと見には、鳥の巣のようなもしゃもしゃした頭の少年は、じっと黙って立っていた。
「不思議なふたり 2」につづく