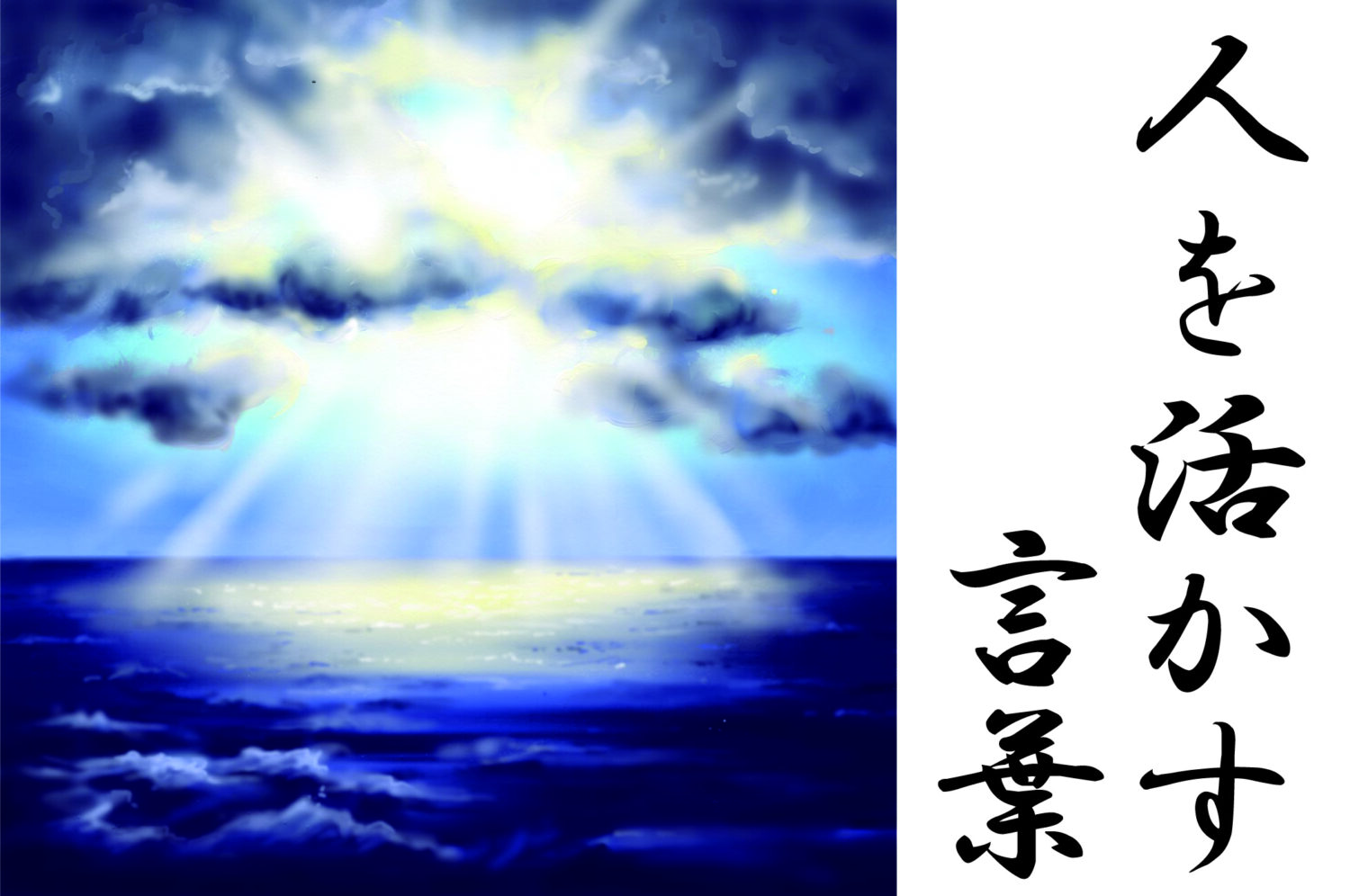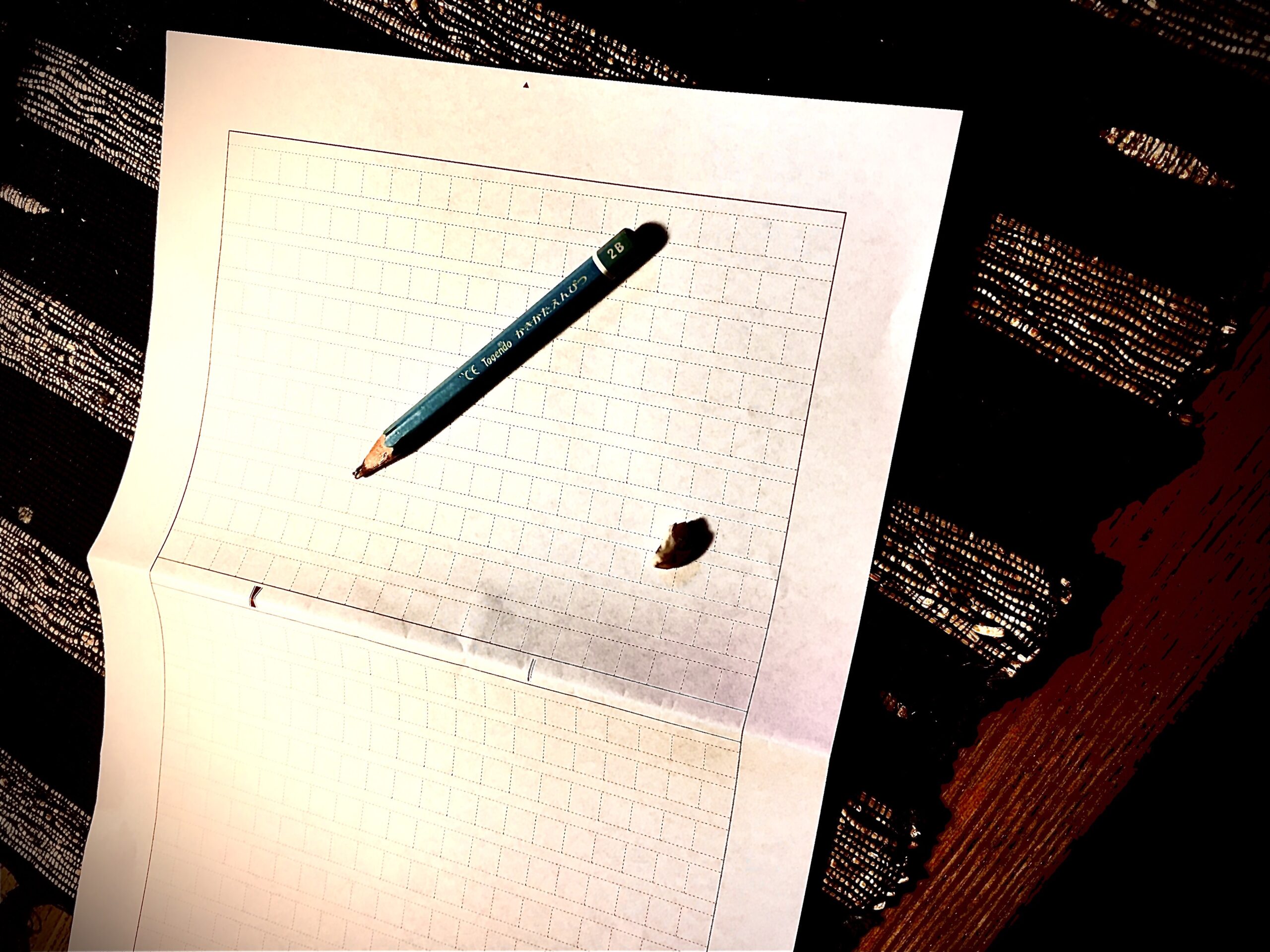少年と怪物
四月
新学期2 〜書かれぬ作文〜
【四月七日同日 午前六時四十分 自宅・居間 インチョー】
インチョーの家の居間は、六畳ひと間で、畳は荒く刈られた田んぼのように毛羽立っていた。
どす黒く光るニスを塗った手製の木の台に、赤く、小さなテレビが乗っている。リモコン式ではなく、もちろんダイヤル式だ。
(マウスが、ひそかに小人用テレビと呼んでいて、うまい言葉だとインチョーは思っていた)。
部屋の中央にある丸い卓袱台は、ペンキがまだらに剥げているうえ、震度一でもみそ汁のお椀が倒れるくらい、ぐらつく。
居間の先にある台所は、一畳半もない。
あとはその横のごく小さな風呂。
自分の部屋と、このふたつと、これがインチョーの家のすべてだ。
母親は、すでに仕事用の服に着替え、朝食を作っていた。エプロンはつけていない。
鼻の奥が潤うような、みそ汁の香りがした。
「おはよう」母が振りむいて言った。
「おはよ」
インチョーは、いまにも空中分解しそうな、古い壁かけ時計を見た。
六時五十分。
母が仕事へ行くまであと十分だ。
七時半前には、本屋のシャッターをあける決まりになっている。
「今日から新学期よね。朝ご飯のまえに支度してらっしゃいな。インチョーさん」
母が手早く、油をひいた熱いフライパンに、卵をふたつ落とした。湯気があがった。
「六年生の委員長はこれから決まるよ、もう委員長じゃない。その話は何度もしたはずだけど」
母がおどけて目を大きくした。
何も入っていないとわかっているが、インチョーは冷蔵庫を開けた。
小便そっくりの黄色い照明がついて、タッパーに入った漬け物と煮物が照らされた。
ほかは調味料だけだ。
掃除機のように、大きなモーター音が鳴った。
年季の入った冷蔵庫は、扉がバカになっている。
小さなころ、きちんと閉めずに、牛乳やもらい物の魚を腐らせたことが何度かあった。
そのたびに母から、頬が焼けるようなビンタを食らって、ヘマをしないようになった。
あのころは小さくてわからなかったが、腐らせたから怒られたのではなく、家計にひどい打撃だったからビンタされたと、今ではわかる。
「電気代がもったいないから早く閉めなさい」
母がぴしゃりと言った。
「眺めてても、空中からごちそうが出てきたりはしないわ。そうならいいけどね」
インチョーは冷蔵庫の扉をきっちりと閉めて、立ちあがった。
台所は狭く、母と並んで立つ格好になった。
「あんた、また背が伸びたわね。もうあたしと変わらないじゃない」
「どうだろう」
「そういえば、結局あれはどうしたの」
「あれって」
「作文よ」
「ああ、うん。ウチは母さんで書けばいいからって、先生が言ってた」
春休みの宿題に作文が出ていた。
題は『父親の仕事について』だ。
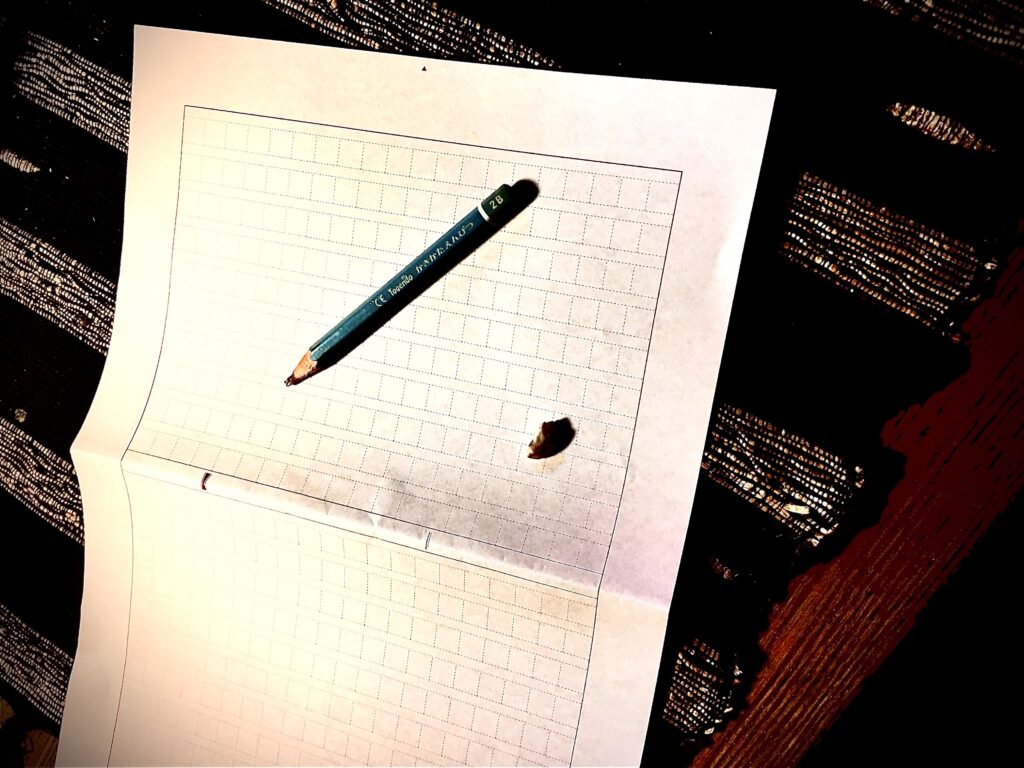
気を遣って、母には言っていなかった。
だから、母さんは学級通信の宿題欄を見たのだと、インチョーは思った。
でも先生が『友だちと話になることもあるだろうから、嫌なら書かなくてもいい』と言ってくれたそれまでは、母は知らない。
父親については、二人のあいだでとてつもない量の会話がなされねばならないはずが、母の返答はいつも通りだった。
「そう」
無数の言葉を隠した、そう。
このたったふた文字が、すべてを覆い隠し、それ以上さぐることを許さない。
だからインチョーは、父親のことをなにひとつ知らない。
だが今日このとき、はじめて、直感めいて思いあたったことがあった。
あのミッキーマウスの時計は、父さんのものじゃないかと。
どこからか、ひとりでにやってきたのではない。
きっと父さんが(それも母さんと)ディズニーランドに行き、買ったものだ。
そう思うと、百万べんも飲みこんできた言葉が喉元までこみあげた。
『母さん。父さんてどんな人』
あるいはもっとソフトに『俺はどっちに似てる?』
どっちもただの言葉だ。言ってしまえ。
父のことを知りたがらない息子が世界のどこに?
なぜ母さんは、ひと言も話さない?
父親はとっくの昔に死んでいると思って、ひどく落ちこんだ事があった。
だから母さんは話さないんだと。父のいない子を、これ以上悲しませないように。
この家に、仏壇は無い。
山の近くにあるお墓に入っているのも、おばあちゃんとおじいちゃんだけ。
養育費もない。月一の面会もない。
それどころか持ち物も、一枚の写真さえ、何から何まで、父に関するものは何もない。
ハカセでなくても、これが、すごく妙なのはわかる。
なぜ、母さんは父さんに関する一切を消したのか。
自分の父親は、だれなのか。
しかしインチョーは、すべてを胸にしまったまま、料理をする母の後頭部をじっと見ながら、いつものように無言でいた。
もし口にしてしまえば、貧乏だがギリギリやれているこの毎日が一気に崩れてしまう、いつもそんな気になるからだった。
そのような予感めいた雰囲気を、母はいつも、無言で発している。
平和の裏で、切れそうなほど緊張の糸が張りつめている何か。
今日の海は寒いだろうかとインチョーは考えた。
何も考えられなくなるほど寒ければいいと思った。
一年生からこれまで、ただの一度も宿題をやらなかったことはなかったが、この作文だけは書くまい、インチョーはそう決めた。
一度決めたら鉄より硬いと、メンバーにあきれられるその性格で、決めた。
母さんが父さんについて忘れようとしているなら、ぼくもそれについて忘れるよう努力しなければならない。
「新学期3 〜実現されぬキャッチボール〜」へつづく
・一覧 「六年生のあゆみ」