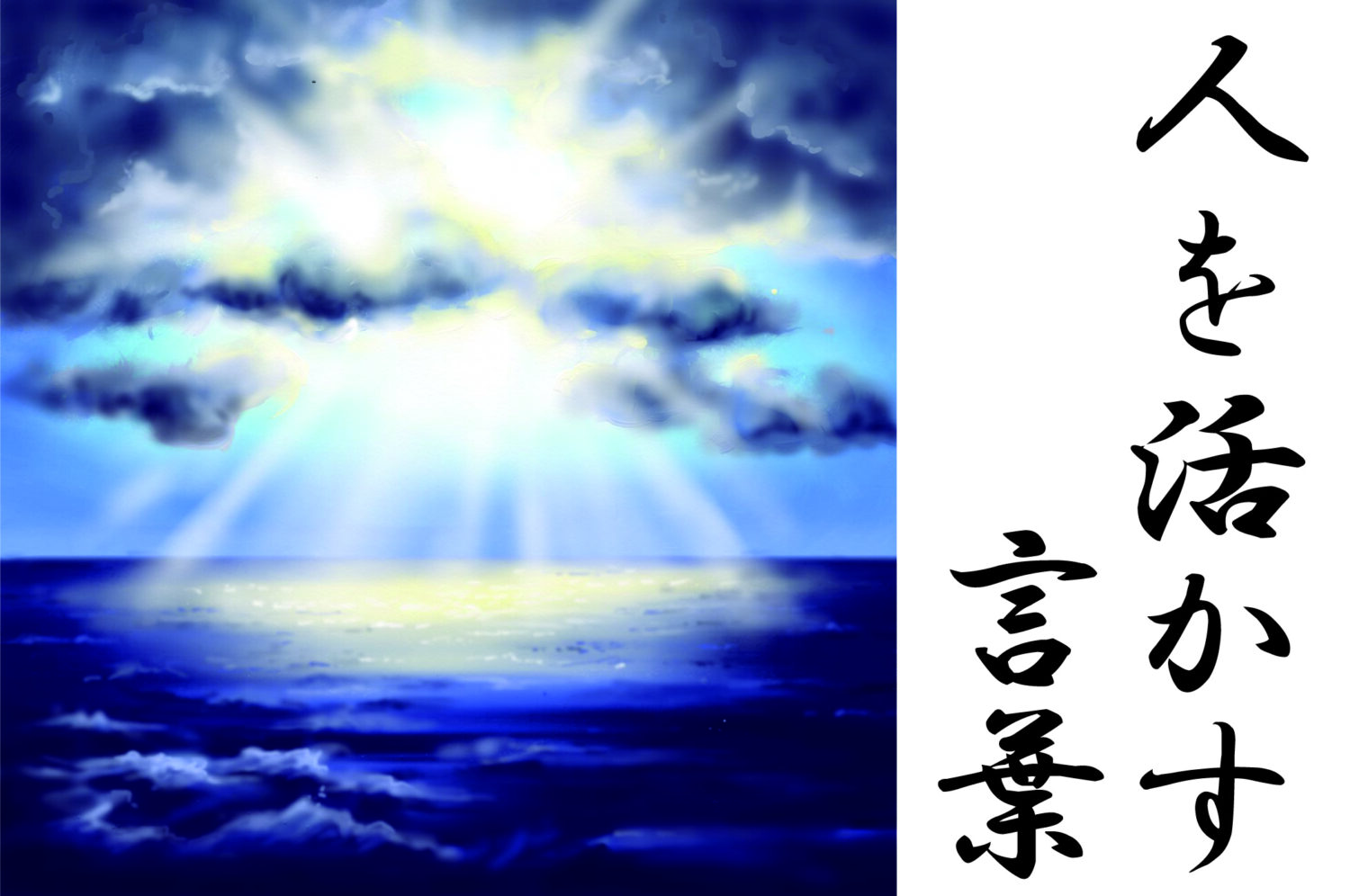※表紙画像 linaberlin
少年と怪物
四月
さいごの会話 〜娘と母のありふれた物語〜
【四月一日 十一時五十五分 網船磯上空 相原江利】
もしあれが最後の会話だとわかっていたのなら、あんな言葉は言わなかった。
そう後悔する人間が、この世にどれだけいることだろうか。
最後の時はわかりようもないが、胸を刺す痛みは一生抜けない。
人生最後の瞬間に、江利もそうしたけっして取り返すことのできない後悔を経験することになったひとりだった。
母親へのさいごの言葉は「こんな家の子に生まれたくなかった」だった。
江利の母もまたそうであって、我が子へのさいごの言葉は「けっこうよ。どうぞ、ほかの家の子になりなさい」だった。

空を飛ぶ江利の頭部が、だんだんと下降曲線にさしかかった。
初恋のつぎ、最後からふたつめに見た走馬灯は、何時間か前、母親とかわした会話だった。
地面の屏風岩が、恐ろしい速さでせまってくる。
どれも先が尖っていて、ただではすまないとわかる。
手をつこうとあがくが、手がない。
それどころか体もなかった。
犬が岩から岩へ、飛び跳ねるようにしてついてくる。
よだれを散らす赤い舌の揺れが目のはしにとまると、その一点へ視点が吸いこまれ、白っぽい点が散らばる赤みが広がり―視界が切りかわった。

【四時間前 七時五十五分 相原家】
「どうしてダメなの」
江利は大声が出そうになるのを、どうにかおさえた。
江利は『海の生き物』のポケット図鑑を持ったまま、居間のテーブルに両手をつくと、母親の背中をにらんだ。
エプロン姿の母親は何も言わなかった。
「どうして磯くらい、ひとりで行っちゃいけないの。すぐそこじゃない。窓からも見える」
朝ごはんの支度をする母は、あまりに忙しすぎて口をどこかに忘れてきたらしかった。
最近もの忘れがひどくなったと言ってたから、きっとそうだ。
「ねえ、ママ! わたしの話を聞いてるの!」
母親が背を向けたまま、湯気の立つ小鍋で味噌をときながら、深いため息をついた。
「どうしてって、あんたも知ってるでしょ。五年生にならないと、ひとりで海にいっちゃいけないって。学校の決まりだってこないだ自分でそう言ってたじゃない。だいたいなんで女の子が海になんかいきたいの。おかしいでしょ」
母が、この世にこれ以上バカな話はないとでも言いたげに、早口で言った。
振り返ろうともしない母に、江利は怒りでこめかみが脈打った気がした。
(なにかをしながら話をきくのは、とても失礼なことだって、いつも言うクセに!)
江利が幼稚園を卒業するタイミングで相原一家が東京の大田区から越してきて、ほぼ丸四年がたっていた。
山と海にかこまれた自然あふれる土地。
のどかな田舎。
静かで、ゆったりと流れる時間。
海外線にポツンと建つ、この辺りではめずらしい洋風の一軒家と裏庭の家庭菜園。

photo by M W 
photo by Rudy and Peter Skitterians
「すべて希望どおり」両親は口をそろえるが、江利にとっては違った。
新しい人生の地は、いきすぎたド田舎だった。
朝起きて窓を開ければいつもわかめを鼻にあてたように潮くさいし、
(おまけに、自転車を一週間に一度磨かないと塩ですぐさびる)、
住んでいる住民はみな、どことなく気味が悪かった。
おかしな決まりもある。
おせっかいで、うわさ好きで、知らんぷりする振りをしながら、耳を巨大にしている宇宙人みたいな人たち。
なにかおかしなことや嫌なことをされたわけではない。
地元の子たちと一緒に小学校にあがったので、いじめにあったとかではない。
(たまによそもんとからかわれたりはする)
海漁町の外の人から見れば、文字どおり江利もいまはどこからどう見ても網船っ子だ。
〔げんつー〕といえばげんこつのことだとわかるし、〔あらかる〕といえば、遠く離れている意味だとも知っている。
しかし四年たった今でも、なじめないものがあった。
そんな中で、はじめて知りたいと思った男の子。
半年も前に会い、それから話せていない。ずっと話したいのに、ぜんぜん叶えられていない。インチョーに会いたい。
今日はどうしても磯にいきたかった。

しかし例の、クソ田舎の妙な決まりが邪魔をする。
「バカらしいったらありゃしない! 変な決まりよ、まったく!」江利は言った。
「ねえママ、だってもう四月よ。今日は四月一日なのよ」
「あんたの屁理屈はきき飽きたわ。そんなくだらないことより、ちょっとはご飯のしたくを手伝ったらどうなの」
母親が豆腐とネギの味噌汁を黒い椀によそった。手元からもうもうと湯気があがった。

江利はわざと音を立てて、椅子を蹴った。
それで母親がとうとう振り返った。眉間に谷のように深いシワが寄っている。
「あんたが言ってたんでしょ。五年生になるのは四月になったらじゃなくて、一学期に入ったらだって。正確にいえば四月七日の始業式が終わったら五年生になるんだって。朝からその不機嫌な顔はなんなの。やめてちょうだい。ほんとイライラする」
(正確には、始業式の校長先生の話が終わったらよ)
江利は心の中で言い返し、お椀をもった。
テーブルへ運ぶと、反抗半分、怒られる怖さ半分で、わざと音を立てて置いた。
味噌汁がこぼれた。
母が目をつりあげたが、恐ろしい目つきをしただけで、首をふり、何も言わなかった。
(ほんと頭にくるわ! くだらない決まりも! ママも!)
江利はアメーバのような形に広がった味噌汁をにらんだ。
春休みに入るまえ、先生から一枚の藁半紙をもらった。
黄ばんでざらついた紙には、宿題や休み中の過ごし方など様々なことがのっていたが、その中の一つに、こういう一文があったのだ。
『みんなは、始業式の、校長先生の話が終わってから新学年です』
なぜそんな決まりがあるのか、意味がわからなかい。
ましてそれが足を引っ張ることになるなんて。

「そうだ! 新年度っていうでしょ。それって四月一日のことだわ。やっぱり今日から私は五年生よ。どこからどう考えても」
「ママはそんなの知らない。もうやめて。十分」
「だってみんなは絶対もう磯に行ってるわ!」
「大きな声をださないでよ」
母親がこめかみをもんだ。
パパが、その仕草をするママは五歳は若く見えると言う顔だが、江利から見ればただ頭が痛いだけの顔だ。
「だいたい、みんなってだれのことよ。エイプリルフールにしてはつまらないウソね。どうせ、言いつけを守らない不良のことでしょ。それより宿題は終わらせたの。学校が始まるまであと一週間よ。わかってるの」
母親が電子レンジで作った目玉焼きをテーブルの上に出した。
江利の嫌いな、ラップで蓋をした、ふにゃふにゃ焼きだ。箸を用意するのも嫌になった。
「今日はどうしても行きたいの! ねえママ、お願い!」
「江利!」母が怒鳴った。
「あんた、いい加減にしなさいよ! これ以上どうでもいい話をつづけるとごはん抜きよ!」
「いらない!」江利は立ちあがった。
母親が、さばいた後の魚の臭いはらわたでも見るような目をした。
「なんでこんな男の子みたいな子になったのかしら。あんたはね、ママのお腹の中におちんちんを忘れてきたのよ」
「なんでそんなこと言うの! もうやだ! あたし家出する!」
「けっこうよ。どうぞ、ほかの家の子になりなさい」
「こんな家の子に生まれたくなかった!」
江利は居間を駆けでると、玄関で靴をつっかけ、外に飛びだした。

「遭遇 〜水切り〜」につづく
・『六年生のあゆみ』 目次