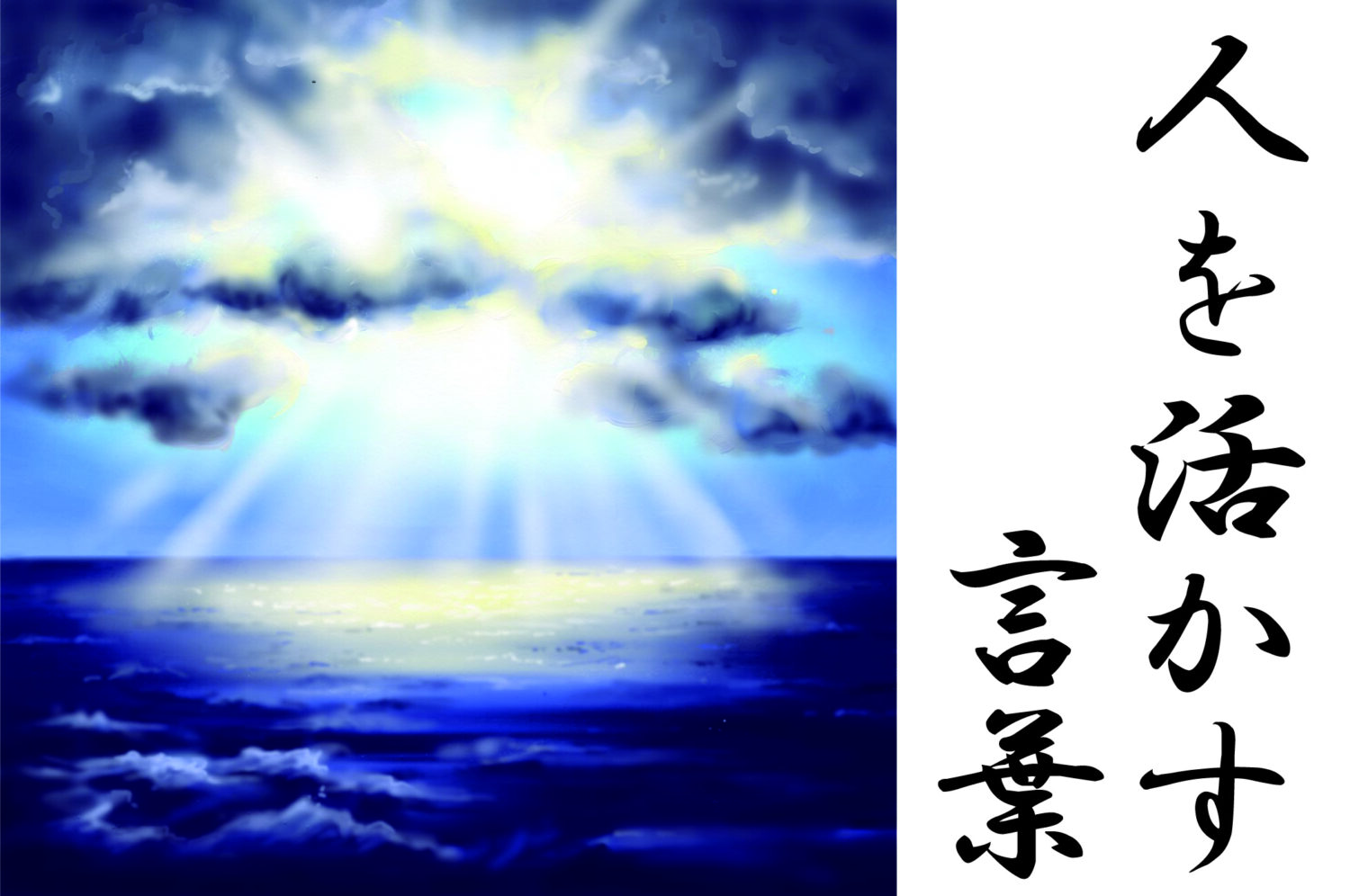※表紙画像 Peter H
少年と怪物
四月
母3 〜思い出の火傷〜
【相原成子 海漁警察署 地下】
突きあたりの階段を降りると、地下はカビ臭かった。
はじめて訪れる成子にも、めったに使われない場所だとわかった。
左右にひとつずつ部屋がある。
「A」と書いてある部屋の前に、若い警察官が立っていた。背が高く、痩せ型で、やけに顔色が悪い。
前をゆく本間刑事とその若い警察官が、無言で頷きあった。
若い警官が金属の扉を押すと、ひどく軋んだ。
室内は明るかった。
普段は物置にしているのだろう、雑多な物を急いで片付けた様子だった。
壁際に積み重なったパイプ椅子と折りたたみ式の長机、丸めたポスターを突っこんだ段ボール、ロッカー、ヘルメット、車止め、青いポリバケツなどがあって、斜めに立てかけた布張りの担架。
そのどれより成子の目をひきつけたのは、部屋の中心に置かれた、銀色に光るステンレスの台だった。

「これです」本間刑事が言った。
調理台のようなその台の上には、おなじくステンレスの四角い盆があり、白い布がかけられていた。
布は盛りあがり、小さな腕の形をしている。
布に赤い染みがあり、成子は息苦しくなった。
本間刑事が白い手袋をつけ、布をわずかにまくって中をのぞきこむと、あらためてゆっくりとまくった。
その腕は、人間の皮膚にみえないほど白かった。
打撲という言葉には到底おさまらない無惨な青痣、何十針と縫うほど長い切り傷も幾つもついている。
腕は手のひらを下にし、台を引っ掻くように指が曲がっていた。
「爪がすべて剥がれてしまっていて、指先は骨が見えているので、そこはあまり見ないほうがいいでしょう」
本間刑事の声は、成子の耳に届いていなかった。
正確にいえば死体の腕を見るまえ、部屋に入ったときから直感、もしくは絆という言葉が正しい何かの予感がしていた。
腕がそれを発していた。
(まさか……そんなまさか!)
「何かわかることがあれば教えて下さい。どんなに小さいことでもいいです」本間刑事が言った。
成子は、それを確かめる手段を知っていた。
そのためには気力を奮い、声を絞り出さねばならなかった。
「刑事さん、手のひらが見たいんです」声がかすれた。

「手のひら? 手のひらですか」
本間刑事は訝ったが、一瞬思案し、切断面があらわにならぬよう、注意深く布を巻きつけるようにし、腕を上向きに置きかえた。
五本の指の先は、骨しかないほど肉が削れていた。
凄く苦しんだと、たやすくわかった。
「指を広げて、手のひらを見せてください」
自分の声は、どこか遠くから聞こえるようだった。
本間刑事が、曲がった指をひらいていく。
硬直した関節が、ポキポキと鳴った。
成子の体が小刻みに揺れだし、呼吸のリズムも乱れに乱れた。
それを認め、成子は身体中のものを吐きだすように、一気に叫んだ。
視界が黒くかわり、世界が傾いた。
「高田!」
気を失う直前、成子は本間刑事の声を聞いた。
切断された腕の、手のひらから前腕にかけて火傷の痕があった。
大きく皮膚がひきつれている。
しかしそれはかなり以前に負ったものだから、完治している。
江利が二歳のとき、コンロのヤカンを倒し、火傷したものだった。
「インチョーという名の少年 〜秘密基地〜」へつづく
・一覧 「六年生のあゆみ」