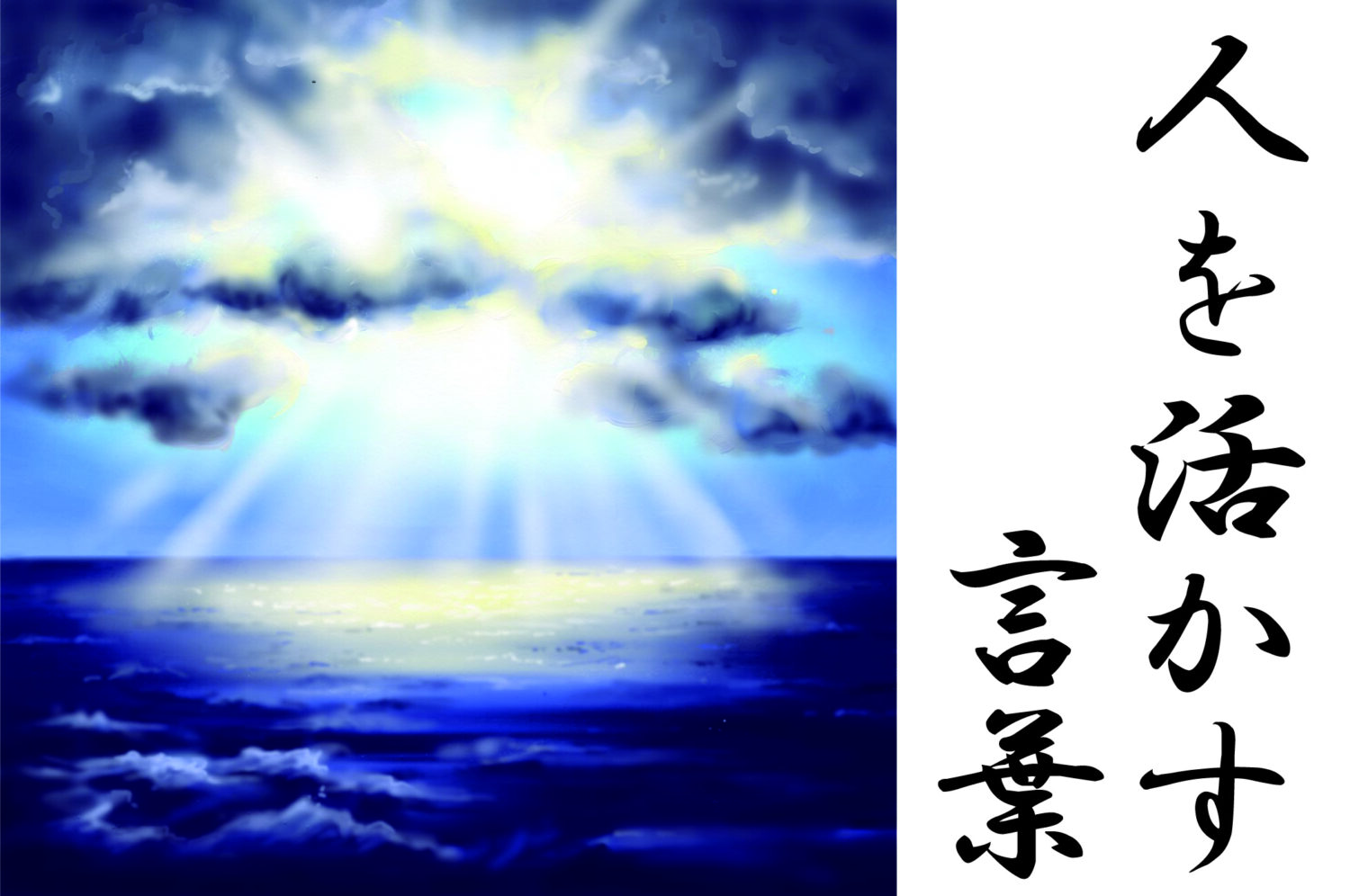少年と怪物
四月
茶ん爺2 〜 チャレンジャー 〜
インチョーは、家につくと、冷蔵庫からタッパにはいった大根ときゅうりの漬け物をだした。朝の残りのみそ汁に火をかける。しばらくして白い湯気がたち、くつくつと沸騰したが、その音がボロい壁にひびく。それほど家は静かだ。
たえきれない。
(もういいだろう)そんなやさしい声がきこえたので、
「うるさい」インチョーはつぶやいた。
電子ジャーにごはんがなかった。袋ラーメンはあった。卵もあった。
すこしかんがえて、どちらもみそ汁にいれた。半熟が好きだ。
テレビをつけてすすった。灰の味だ。だから漬け物をいれた。ぽりぽりと歯ごたえがいい。でもやっぱり灰の味だ。

なぜ食事のときはテレビをつけちゃいけないと言われるのか? めんどうくさい。口を動かすのはさらにめんどうくさい。でもはらが減ってイライラするよりマシだ。
そもそもチャンネルなんか、なんでもいい。なんでもよかった。こういうことをかんがえなくてすむなら。
俺は今、何をかんがえてるんだ? まともなのか?
とにかく灰の味がいやだが、テレビごときじゃどうにもならない。
そういえば、本を読んだらもっと行儀が悪いといわれるだろう。なぜなのか。
食器を洗う。朝とおなじく干す。朝にもどった気がする。歯磨きをする。歯磨き粉は甘い。灰じゃないぞ。うまいじゃないか。
チューブを吸って、ぎゅっとにぎり、飲んだ。
今日もまた、独りの日課が終わって、たえがたい静かな家をでた。
俺がいてもいなくても、この家はかわらず静かだ。このさきもずっと。それは、気がくるいそうなことだ。
家の裏手にとめてある自転車をもってきた。
真っ黒で、いまどき、店に売ってないほど古い型。フレームもタイヤも極端に太い。角材でつくったみたいに、どこもかくばっている。でも手入れはキレイにされている。そうしろと、茶ん爺にきつく言われた。
インチョーは愛用の自転車《チャレンジャー》にまたがると、ペダルをこぎだした。
チャレンジャーとは、コナン・ドイルの小説『失われた世界』にでてくる主人公―勇敢な教授の名前だ。猿に似た風貌だが、頭脳明晰で活力にあふれた人だ。
グループの名前《失われた世界》も、秘密基地がある《メイプルホワイト台地》も、この小説からきていた。
(そういえばあの子、どうしてるのかな)
言葉のうまく話せない、片手の子。グループができるきっかけとなったあの子。
(あの子―アッチンはどこにいるんだろうか)
インチョーは体をまえに乗りだすと、ふとももにぎゅっと力をこめた。
海へつながるまっすぐなアスファルトの下り坂を、ぐんぐんスピードを上げていく。

速く。もっと速く。
スピードをあげればあげるほど、心の重りが消えていく。
向かい風に髪が巻きあがる。
潮の香りを胸いっぱいにすいこむ。
風の中の塩の粒が、鼻の奥や肺の奥を洗っては、でていく。
スピードをあげすぎて、ハンドルが小刻みにぶれはじめた。これ以上、速くなれば転ぶ。
インチョーは、逆に、もっともっとペダルをまわした。ブレーキなどかけない。
転倒したらただではすまない速度になっていく。背筋がゾクゾクした。
ハンドルが制御不能になって、バランスをくずした瞬間、ようやうチャレンジャーが目を覚ました。
ぶっといフレームの中から、モーターがまわるときのような、クオーンという音がきこえた。
タイヤががっちりと地面をかんで、ハンドルがピタッとさだまった。
「……いけ! チャレンジャー!」
チャレンジャーは息づき、今や自走しだした。
速度がますますあがった。
前方に見えた田んぼと畑が、あっという間に後方へ流れる。
耳の中で風が鳴り、服のすそがはためいて体にビタビタあたる。
急カーブにさしかかった。
インチョーはハンドルを握りしめると、一発の弾丸と化したようにつっこんだ。
道路の外側いっぱいに位置をとる。
バイクレーサーのように重心を倒して、曲がりながら内側へ入っていく。
地面と膝がつきそうなくらい体がかたむいた。
だがチャレンジャーは、地面に吸いついているように、ビクともしなかった。
ノンブレーキでカーブをすぎさった。
この芸当をメンバーにみせると、大喜びする。
そういえばマウスが「ぼくも!」と言って、ものの見事にすっ転び、肘を四針ぬったことがあった。
そんな思い出も、風のように頭をすぎさった。
『チャレンジャーに乗りたい!』と、メンバーがかわるがわる乗ったこともある。
でもチャレンジャーは、インチョー以外のだれが乗っても目を覚まさない。
みんなが首をひねった。でもインチョーはわかっていた。
チャレンジャーには心がある。特別な自転車なのだ。
・目次 「六年生のあゆみ」