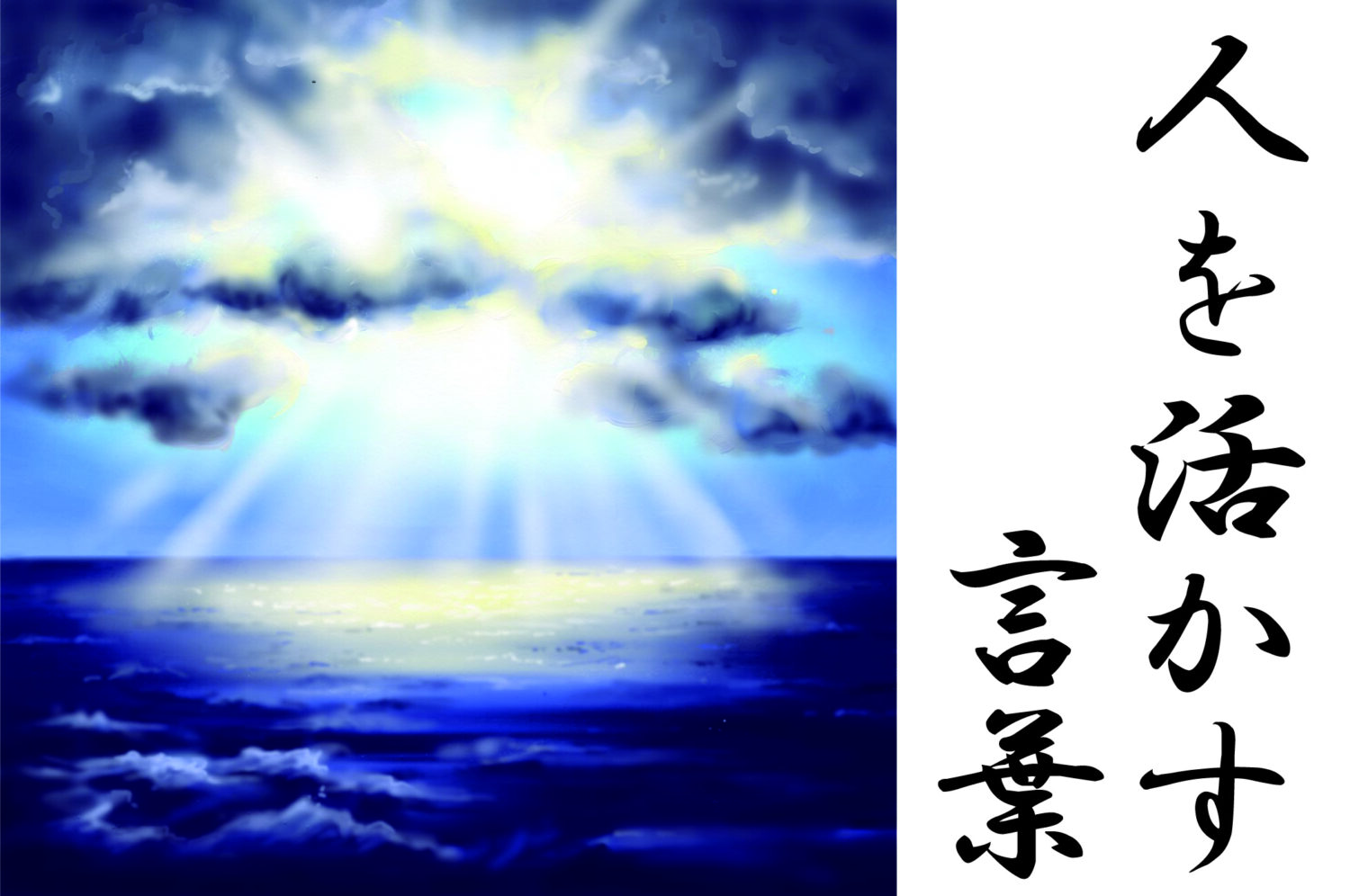少年と怪物
四月
インチョーという名の少年2 〜マウスの大変話〜
「そう! それが映画みたいな話なんだ! 相原江利って子、インチョーも知ってるでしょ。インチョーとダイの後をくっついてきてた、いっこ下の子だよ。覚えてない? 死んだのはあの子なんだ!」マウスが言った。
もちろん覚えがあった。
半年前、本校舎でダイと一緒にいて、六年の上級生たちと喧嘩になったことがあった。
そのとき階段の陰にいた女の子だ。図書室でもなんども見かけている。
おさげで、気の強そうなつり目の女の子だ。
インチョーは本を閉じて脇に抱え、ふっと息を吐くと、三メートル以上の高さのハンモックから飛び降りた。
膝のクッションをきかせて、落ち葉が積もった地面に左手をつき、柔らかく着地した。
手の平についた落ち葉や土をはらうと、マウスが口笛を鳴らした。

「あの子が死んで、その死体が海岸で見つかったのか」
「うん。それもバラバラなんだよ! バラバラ! 昨日右手が見つかったんだ! 昨日だから最初エイプリルフールだと思ったんだけどさ、なんだかほら、海のほうでパトカーがすごかったでしょ? 暴走族を追っかけてるのかとぼく思ったんだけどさ。安治おじさんが昨日の夕方、見にいったんだよ。警察が柵なんかで囲っちゃって近くまでいけなかったらしいけどさ、もー、廃穴のまわりが血だらけだったんだって!」
マウスが、まるで機関銃のように早口で喋った。
それがまた語り口がうまく、身振り手振りもおかしく、さらに人真似まではさむものだから、興味を惹きつけずにはいられないのだった。
「安おじさんが今日の朝、ぼくん家にきて言ったんだ。ありゃあな、ペンキなんかでねえど、ほんまもんの血だあど。空気に触れっとよ、血はまっ黒ぉくなんだぞって。安おじさんが死体を見つけてたら凄かったんだけどなあ」
マウスが片眉をあげ、手鼻をかむ真似をしながら言った。
インチョーは黙って、うなずいた。
どうやらマウスお得意の〔大変話〕にたまに混じる、真実の話らしかった。
「それ、本当か。死体なんて」インチョーは言った。
「本当だよ、おじさんが言ってたんだから」
「春休みに入るまえ、十メートルもあるガラガラヘビが田んぼを横切って、ぼくを睨んでシューッて喉を鳴らしたって話してたじゃないか。ぼくの腕より長い牙で噛みついてきたのを、間一髪で避けたって。それでダイが、ガラガラ蛇なら鳴き声はガラガラじゃねえのかって―」
「悪かったよ! あれは、そう、ガラガラヘビじゃなくて青大将かマムシだった。せいぜい四メートルかな」マウスが両手を大きく広げた。
インチョーは笑った。
「そのすこし前は雪男だった」インチョーは言った。「山の上の、上神社のほうに逃げたって。どでかくて、目が赤く光ってて、ボロボロの布を体に巻きつけてて、子どもをさらって、壁に杭で打ちつけて干物を作ってるって言ったぞ」
これもまた、どこをつついても穴だらけの話で、そもそも温暖な南房総では、せいぜい五〜六年に一度しか雪が降らない。積もったことなどインチョーが生まれてから数えるほどで、それも朝十時くらいまでにすべて溶けてしまう。
「あ、それは本当だよ! 雪男かどうか知らないけど、獣みたいな人間が逃げていったのは本当に見たんだ……わかったよ! 子どもをさらうところから先は、ぼくが作った話なのは認めるって!」
「右手だけ見つかったなら、死んだかどうかわからないんじゃないか」
インチョーは振り回されぬよう用心して聞いた。
マウスがしてやったりという笑みを浮かべた。
「さすがインチョー! やっぱり気づいたね! でも甘いな。話にはつづきがあるんだ。これも安おじさんに聞いたんだけど、江利のお母さんが警察に呼ばれたんだって。それで死体置き場でその手を見て、江利のだ! って叫んで、頭がおかしくなったんだって」マウスが頭の横でひとさし指を回した。
「おかしくなった?」
「安おじさんは、はっきり言わなかったけど、気が変になったってことだと思う。で、さっきなんだ! 安おじさんが仕事にいってさ、ぼくが廃穴にいこうとしてたらさ、パトカーがわんさか海道をぶっ飛ばしてったわけ! それで急いで自転車で追っかけたんだ。大変なことが起きたってぼくにはすぐにわかったね。パトカーはどこに集まってたと思う」
「廃穴か」
「はずれ! 浜駄菓だったんだ! おまわりさんがめちゃくちゃいてさ、浜駄菓が黄色いテープでぐるぐる巻きになったみたいでさ、浜駄菓が犯人で捕まったみたいだったよ。それでぼく、お巡りさんと大人たちの話を聞いたんだ」
浜駄菓は海道沿いの駄菓子屋だ。本当はクリーニング屋だが、アイスは売っているのでそう呼ばれていた。
「そしたら今度は頭が見つかったんだよ! いや、首っていったほうがいいかな」
マウスが首をかしげた。
「とにかく江利って子の首から上! それも目玉が飛びでてて、もうむちゃくちゃだったらしいよ。浜駄菓のおっちゃんが見つけたんだ! あのおっちゃん、ほら、いつも猫とか犬にエサあげてるじゃない? 野良犬の一匹が首をくわえてきて、エサをいれてる皿に置いたんだって。その犬、おっちゃんにお礼をしたつもりだったのかもね。浜駄菓のおっちゃんさ、警察に、最初でっかいマリモかと思ったって言ったよ。でも、丸い玉が垂れ下がってて、それが目玉でぎろっと睨まれて、気絶するかと思ったって、おっちゃん、青い顔で死にそうな顔しててさ。あれはたぶん、驚きすぎてすいぞーとかどっか内臓がひとつぶっ壊れたんじゃないかな。それで、その生首なんだけど、よく見ると輪切りになってて、それが皮一枚でつながってたんだって。警察はそこらの犬を全部捕まえるっていってたよ。全部かいぼーして胃の中を確かめるって。でもさ、野犬の群れに襲われても、首だけ残して食べられちゃうなんて、そんなことあると思う? そしたらおっちゃんが、犬は殺すんでねえ! って急に怒鳴りだしてさ、まあ凄い騒ぎだったよ」
本当だとしたら身の毛のよだつ話だった。
マウスは無邪気に話すが、インチョーは話を聞くうち真剣になっていた。
「じゃあみんな、なんで浜駄菓じゃなくてプール下にいったんだ」
「昨日右手、今日が頭でしょ? ほかにも絶対まだあるって警察も大人も言ってたからさ。それをぼくたちで先に見つけようってみんなに電話したわけ」
一日はまだ始まったばかりで、まだまだ探す時間はある。
それに、たとえ陽が落ちるまで探しても、インチョーの家には誰もいなかった。
「よし、決まり!」マウスが駆けだした。
インチョーは丸めてあった雨よけの青いビニールシートを投げ上げて、手早くハンモックにかぶせると紐で縛り、マウスの後を追った。
・一覧 「六年生のあゆみ」