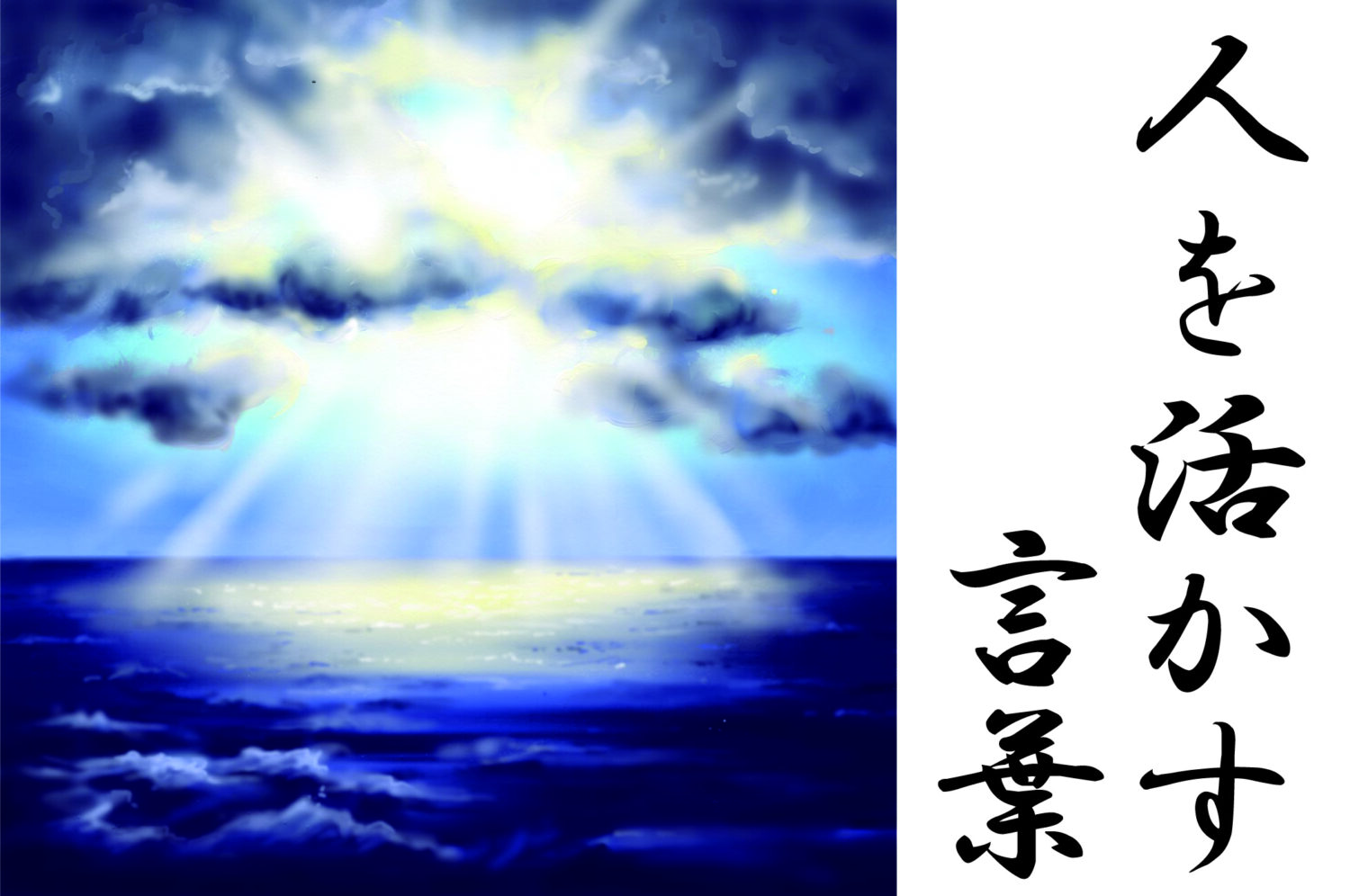少年と怪物
四月
新学期3 実現されぬキャッチボール
【四月七日 六時五十五分 インチョー 自宅・台所】
「母さん」インチョーは言った。
「なに?」
「朝ご飯くらい自分で作るよ。もう仕事にいく支度をしたら」
母親がこちらを横目で見ると、鳥の首でも絞めるようにほうれん草の束をつかんでまな板に乗せ、包丁で根を切り落とした。
そして、根の間の泥をすすぎはじめた。
「そう? それは結構ね。ありがとう。でもね、これは母親の仕事なの。たしかにあんたに任せることもできる。あんたなら、それはやれる。だけどあたしがやることだからやってるのよ。おわかり?」
母が濡れたほうれん草を、叩きつけるようにしてまな板に置いた。
手荒に切りはじめたが、すぐにやめると、包丁の刃を親指でなぞった。
「ああ、もう! なんでこんなに切れないの! このクソったれのナマクラ!」
インチョーが口にした何かが、母の気にさわったらしかった。
インチョーは黙って、つづきを待った。
『相手の話は最後まで聞く』
『どんなに口をはさみたくなっても、相手に話す気配をちょっとでも感じたら、口を閉じておく』
インチョーは、こうした母の教えを頑なに守っていた。
たとえ、教えた本人を前にしても、それはおなじことだった。
短く揃えられたほうれん草が味噌汁鍋に消えた。
母が、何色だからわからないほど褪せたチューリップ柄のエプロンで手を拭き、インチョーへ向きなおった。
インチョーの思った通りだった。
「余計な心配はいいから、今日からしっかり勉強しなさい。朝ご飯なんか作れなくってもいい。そのかわり、斎くんとおなじくらい頭が良くなって欲しいわ。いい? あんたはちゃんと、お給料のいい会社に勤めるの。こんな田舎じゃなくて、都会にいくの。ちゃんと勉強して、いい大学に入らなきゃ今はダメなのよ」
母は一気にまくしたてると、海苔を炙り、細かくもんで納豆とあわせた。
「あたしの役目はあんたのエサ係。あんたの役目は勉強係。わかる?」
斎くんとは〔失われた世界〕のメンバー、ハカセのことだ。
ハカセは、算数・国語・社会・理科の主要四科目でいつも一番だ(でも国語だけは同着一位の時もある)。
インチョーはうなずいたが、やはり何も言わずにいた。
母に苛立ちをぶつけられて、何も言えなかったのではない。
頭の中で、幼いころから繰り返し聞かされてきた母の声が、呪いのごとく響いていた。
『鼻を触るとか、右上を見るとか、そういう仕草よ。あと話の内容。何を大事だと思っているのか。ほかにも、声から聞きとれる気持ち、あとこまかな表情なんかよ。いい? 話を聞くときは、相手をよく見なさい。息の吸い方は普通か。目の動きはどうか。喋り方はどうか。速くなったり、わざと遅くなってないか。相手の話をちゃんと聞きながら、体の動きとか、音なんかもぜんぶ見るの。本当の意味で、相手を見るのって、みんなができる事じゃない。ほんのひと握りの人だけ。とっても難しいの。でもそれができたなら、相手が本当は何を言いたいのか、何をやりたいのか、超能力みたいにわかるようになる』
こうしたことを初めて聞かされたのは、幼稚園の年少で、足にひどい怪我をして、泣いていた時だったと思う。
母さんが顔を赤くして怒りながら、話を聞くということについて怒鳴るように話し、
おれは、血に染まった足首を抱えて泣いていた。
話が頭に入るどころではなかった。
(大変だ。ぼくの足、つま先が反対をむいちゃってるぞ)
母さんは、息子の足が180度ねじれているのには目もくれず、息子の頬を両手で挟み、息子の目をまっすぐに見据えながら、話し続けた。
母の教えは、意味がわからなかった。
でも、意味は大事なことではない。
大事なのは、母さんがこれを大事だと思っていること。
そして息子に、それをできるようになってほしいと強く思っていることだ。
だから毎日、飽きるほど試してきた。
母さんの教えは絶対だ。
ましてこの世に唯一の肉親だ。神の言葉より重い。
つまるところ、幼稚園の年中の夏くらいまでに、インチョーは口をぎゅっとつぐみ、相手を〈見〉ることを身につけていた。
人との関わりで重要なのは観察。至上の命令。鉄則。
代償として得たのは、いきすぎた無口だ。
しばし沈黙が流れ、母が口をひらいた。
これもインチョーの思った通りだった。
母親の役目をこなしていない、そう息子に言われたと思って、母さんは怒った。
でも怒りの大元は、息子に一分一秒でも勉強させたいあらわれだった。
いい大学に入り、いい会社で正社員とかいうものになって欲しいことのあらわれ。
でもその下の下に、まだ何かが隠れている。
それがわかる。
この次、母さんの口から出ることこそが、本当に母さんを怒らせ、その心を乱し、母さんの頭に長年、寄生虫のように棲んでいるものなのだ。
だがそれは、インチョーがまったく予期していないものだった。
母が、うつむき加減で言った。
「今日、母さんが仕事から帰ってきたら、キャッチボールしようか」
聞き違えたかと思った。
しかしたしかにそう言った。
母親は恥ずかしげな顔で、料理の手を止めて、まな板とにらめっこしている。
「子供と遊んだりするのも、親のつとめでしょう? まあ、本当は父親なんだろうけど。母親とキャッチボールしたって悪いことはないわよね」
母は毎朝五時半に起きて弁当を作り、七時半には、まだ走っているのが不思議になるくらいオンボロの軽自動車で、本町の本屋に働きにいく。
帰ってくるのは、早くて夜八時、遅ければ十時をまわる。
月曜から土曜の週六日勤務で、日曜も月に一、二度は働く。
だからインチョーは、何と返事をしていいかわからなかった。
父親についての作文課題がきっかけだとわかるが、母の意図はまったくわからなかった。
『インチョーの母ちゃんて、けっこう美人だよなあ』とメンバーがからかうその母が、引き締まった腰に手をあてると、意を決したように顔をあげた。
その眉間に、深い縦じわが刻まれていた。
「そうよね、やっぱり嫌よね。母親とくだらない球の投げっこだなんて。ほんとバカバカしい。くだらない。あたし、どうかしてる……変な事こと言って、悪かったわ」
母が吐き捨てるように言うと、背を向けた。
味噌汁鍋がコトコトと沸騰する音だけが、やけに響いた。
別にやってもいいよ。
インチョーはそう言いたかった。
だが不思議と、その言葉が喉でつかえてどうしてもでない。
たしかに恥ずかしい。
六年にもなって母親とキャッチボールなんて。
もしクラスの誰かに見られたら、一生バカにされる。
でも、今まで、ただの一度もやったことのないキャッチボールを、なぜ母さんが、今、やろうと言い出したのか、その意味がわからないから、素直にうんと言えなかった。
「そもそもあたしが帰ってくるのなんて夜よ。何も見えやしないわ。ほんと、あたし今日はどうかしてるわ」
母が、自分に腹を立てたように言った。
人生で、取り返しのつかない失敗をしたことに、たった今気づいたような言い方だった。
「……懐中電灯」インチョーは言った。
「なに?」
「夜にキャッチボールをするなら懐中電灯がいる」
暗闇の中で、頭に懐中電灯を縛りつけて、母と自分がキャッチボールしている姿を、インチョーは想像したのだった。
母は、何を言われたか理解できないという顔をした。だが、
「……そうね」と微笑んだ。
朝の光が、その顔を照らした。
「投げるたびに、草むらを探すはめになると思う。おれは野球が下手だし、母さんもうまくないと思うから」
「そうね。じゃあキャッチボールはまた今度にしましょうか」
「そうだね、また今度だね」

絶対にそんな機会が訪れないことは、互いにわかっていた。
でもそれでも分かりあえた。
母さんが、父さんのいないことをやはり気にしていたこと。
息子もそれを気にしていたと、母さんが知ったこと。
母親がなぜ、キャッチボールをしようなどと突然言い出したのか。
母なりに、父親のいない穴を埋めようと必死だったと、インチョーはだいぶ後になって知った。
ただこのときは、母のひさしぶりの笑顔が、ただただ嬉しかった。
時が過ぎるにつれて、母は笑うことが少なくなっていた。
今では一ヶ月に一度、笑うかどうかだ。
良いタイミングと思えて、インチョーは部屋へもどると、学校へ行く仕度をした。
手をすすぐ音が聞こえてきた。
水道の水は、目を凝らせばほんのわずかに赤みを帯びていたが、インチョーも母も気づくことはなかった。
「小学校1 〜誰しもの記憶〜」へつづく
・一覧 「六年生のあゆみ」