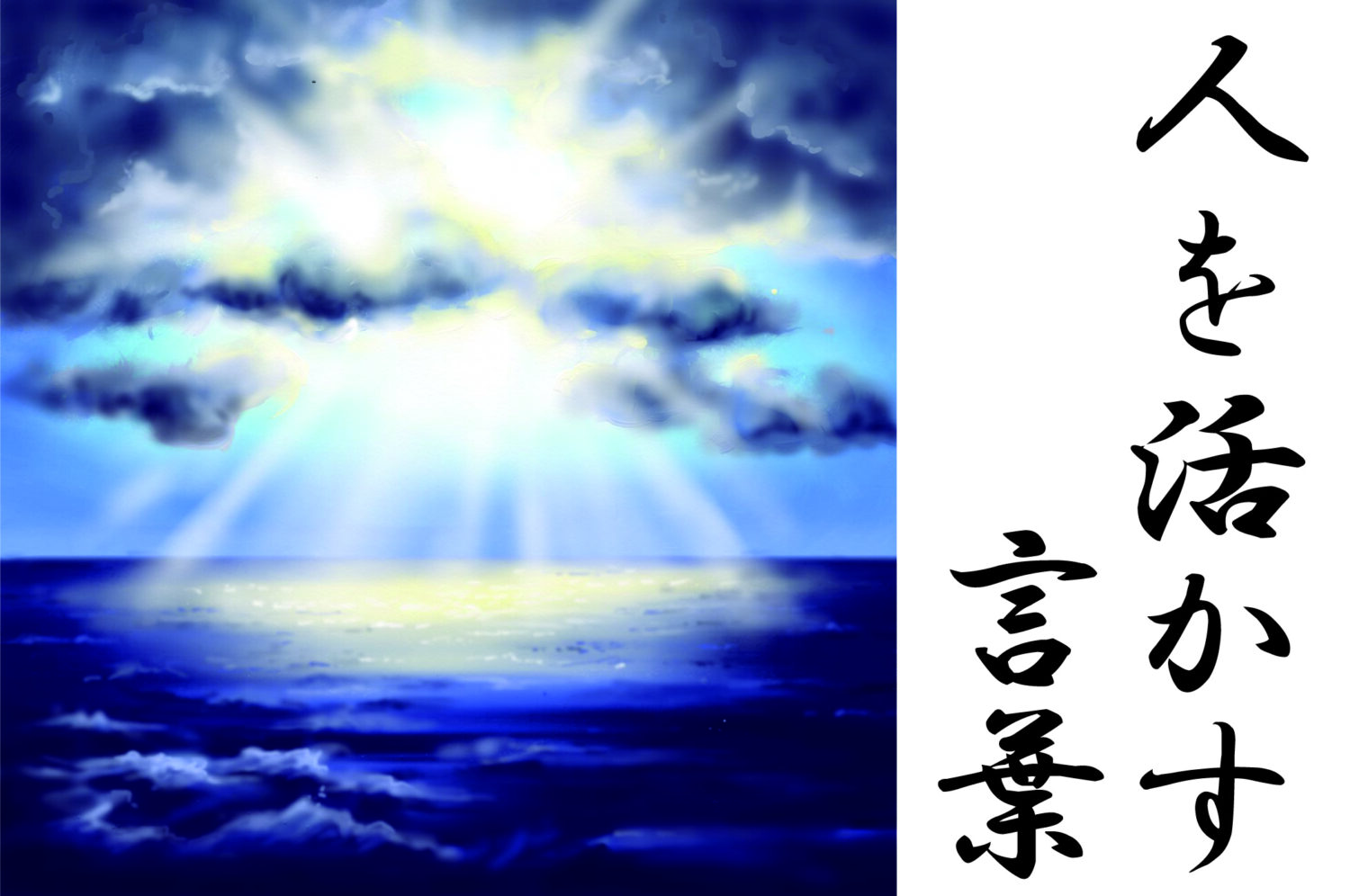※表紙画像 Dale86
少年と怪物
四月
帰らぬ子 〜母の直感〜
【四月一日、昼 自宅 相原成子】
江利の母―相原成子は、海漁町民のすべてが地獄行きとすれば、娘につづいて二番目に切符を手にすることになった。
広報のサイレンが昼を知らせる〈エーデルワイス〉を鳴らした。
『ただいま』が聞こえないか耳をすます。しかし、サイレンは鳴り終わった。
昼は十二時、夜は七時。
食事の時間に一分たりとも遅れてはいけないのが相原家の決まりだ。

娘のはじめての家出。
成子は頭痛がして、こめかみを揉んだ。
すべての母親とおなじく相原成子もまた、たいしたことはない、私もそうだったじゃないのと、昔を思いだして自分を納得させようとつとめ、気をまぎらわすための家事をはじめた。
しかし、一分もしないうち〔もし〕がうかぶ。
こんな田舎に、ニュースでやるような理解不能の(たとえばいま埼玉と東京で起きている恐ろしい幼女連続誘拐殺人を起こすような)人間はいない。
だが、十歳の少女にいたずらをする大人がゼロかと言われれば……。
人目につかない場所は、どこにでもある。

あるいは、年がら年中、それこそ真冬でもやってくるサーファーたちはどうか。
花の時期が終わったいま、そろって色素の抜けた金髪と小麦色に焼けた肌の男女が、分裂でもしたように押し寄せている。
見通しのいい海岸線を、彼らはご自慢の車で狂ったように飛ばしまくる(だいたいトヨタのSUVかミニバンだ)。
かなり遠くだと見当をつけて道路を渡ると、アスファルトを削るタイヤの音がおどろくほど迫っていて、冷や汗をかくことがある。
テレビで目にする水場の事故も思い浮かんだ。
友達と遊びにきて海で溺れた中学生、浅瀬で遊んでいて父親が気づいたときには姿が見えなかった小学生の女の子。
用水池や防空壕、都会に無い危険な場所も多い。
江利はこの町になじめないのだろうか。
夫と私の念願の田舎暮らしだったが、江利が嫌っているのは明らかだ。
『人間に興味をもってる宇宙人みたいな人がおおいの』
江利が言うように、すこし、たしかにほんのすこしばかり変わった人はいる。
たとえば五十メートル以上も離れているのに『ご近所さんね』と、ことあるごとに顔をだす小山のおばあさんのように。
小山のお節介ばあさんは表に出るたび、こちらを気味の悪い目つきでじっと見てくる。
『よそ者が悪さしないか、あたしが見張ってるの』と言わんばかりで、思わず、やめてくださいと叫びたくなる。
おまけに花壇に小便をまくから、東から風が吹くとひどい臭いが漂ってくる(トイレが壊れているのかボケているのか、微妙な線だ。いや、ボケているのだろう)。
成子は、湯気の消えていくオムライスを、腹立たしい思いで見つめた。

片付けも洗い物も終わってしまい、テレビのチャンネルを次々にかえていく。
イグアナ芸の芸人タモリがあてた『笑っていいとも』、二月のリクルート事件からつづいて春の改編があったのにちっともかわり映えしないつまらない番組を見ながら、江利をどんな風に叱ろうか考えた。
重要なのは、この失敗をもって江利にどんな教訓を学ばせるかだ。
自ら学ばねば、人は変わらない。
しかし江利がおとなしく話をきくとも思えない。
(一度、家族三人で話しあいの場をもつべきかもしれない)
そう思うほど、最近の江利はひどい。
それともうちの子だけがそうで、みながそうなのだろうか。
世間の母親は、娘に反抗期の兆しがあらわれたとき、どのような話をするのだろうか。
見当もつかなかった。
このごろの江利は、父親におそろしく似てきた。
自分勝手に物を言うときの、あの口の尖らせ方。気味が悪いほどだ。
江利はあの人の、悪いところばかりを集めて出来たように思える。
若いころは、キラキラとした目で『おれは好きな場所に住む。田舎の、潮の香りが胸いっぱいに吸える海辺の町なんかがいい』と、将来のことをかけらも心配せず自信たっぷりだった夫のことが、とても素敵に見えた。
だが現実は、残酷なまでに現実的だ。
田舎の暮らしと引き換えに収入は半分になった。
そこらじゅうが虫だらけで、ご近所づきあいは煩わしく、買い物は不便きわまりない。
わたしの、水産加工場でのしらすのパック詰めと、夫の米屋の配達ではやりくりがやっとなのに、夫の酒量も増えた。
(今日も飲んで深夜に帰ってくるだろう。消防団の集まりらしいが、毎週三回も何を訓練するのか。『付き合いで行かなきゃいけない』が夫の口癖だ)
だんだんと怒りの対象に夫も加わっていった。
成子はぶつぶつと、二人に文句を言いながら待った。
しかしフクロウの壁掛け時計が十三時を知らせると、泳いだ瞳で時計を見つめた。
(……おかしい。いくら何でも遅すぎる。誰かの家にいったなら電話でもくるはずなのに)
テレビの中の、わざとらしく付け足したおきまりの笑いが、やけに勘にさわった。
それでも辛抱して待った。
だが我慢の限界は、長針が真横を指すまでだった。
『たいしたことないさ。いつも大げさだな。江利が足の指を骨折したっておまえが騒いだときも、ただの深爪だったじゃないか。遊んでて時間を忘れたのさ』
実際は逆なのに、なんでもわかってる風の夫のあざけりがうかんだが、成子は立ちあがり、褪せたクリーム色のコートをはおると、食卓に新聞紙を広げてかぶせた。
場所は見当がつく。朝、話をしたばかりだ。
言いつけを守らず網船磯にいったに決まっていた。
(女の子がひとりで磯に遊びにいきたいなんて)
もしや、クラスに男の子が十五人しかいないのに好きな男の子でもできたのだろうか。
そう思った瞬間、息が止まるほど、胸が苦しくなった。
不可解な、刺すような痛みは一瞬で消えた。
言い知れぬ不安が、一秒ごとに大きくなり、心を揺さぶりはじめた。
「帰らぬ子2 〜桜の花びら〜」へつづく
・目次「六年生のあゆみ」