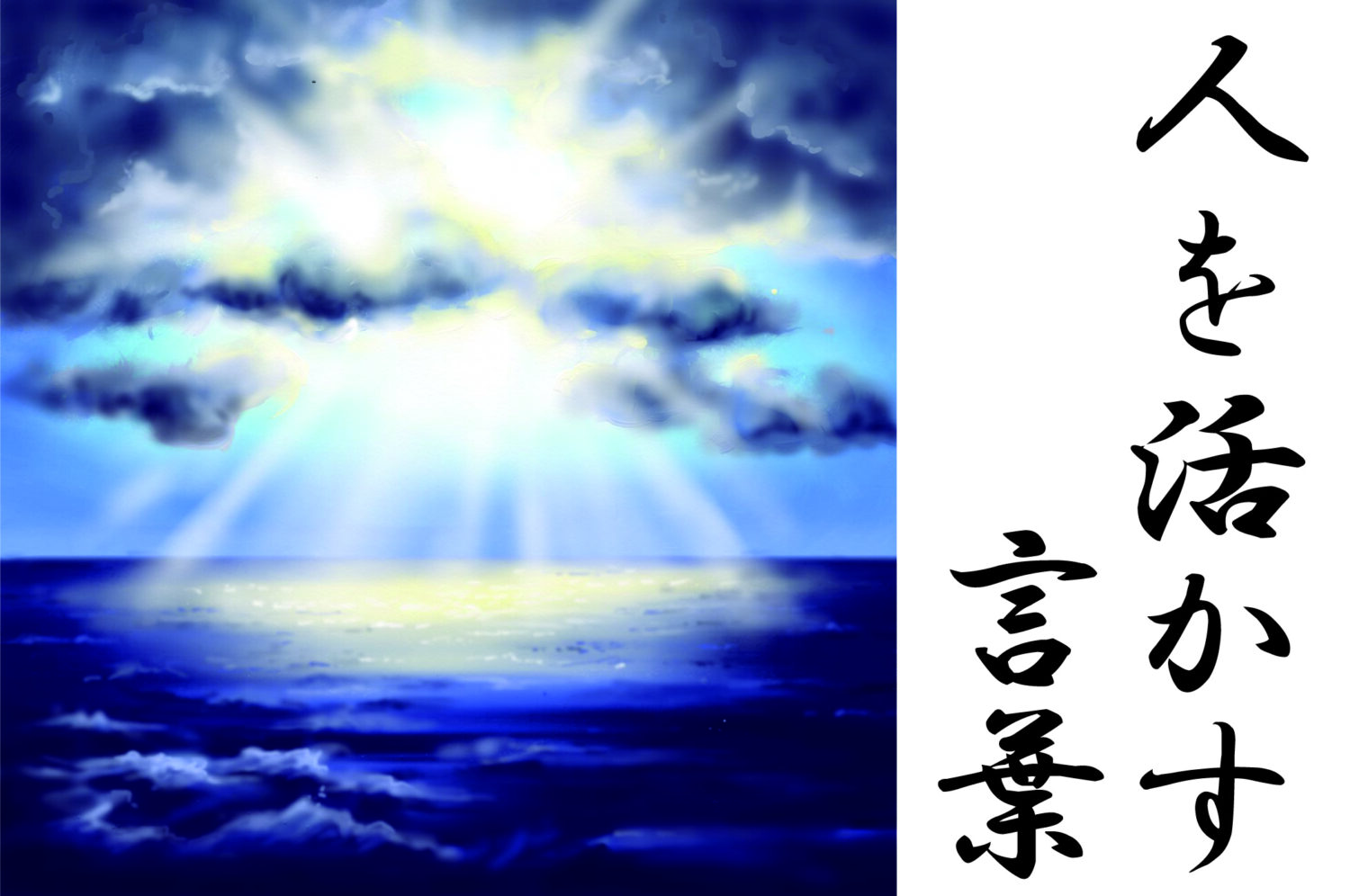少年と怪物
四月
展望岩と廃穴
腿の裏を、暖かく濡れたものに舐めあげられ、江利は悲鳴をあげた。
野良犬が黒い目で見あげていた。太い尻尾を振っている。
大人ほども大きく、江利はたじろいだが、犬の瞳は賢そうだった。
江利はあまり犬に詳しくなかったが、ハスキー犬のようだった。
江利はぐるりを見回した。
「あんた、飼い主は?」
犬は陸のほうへ何歩かいくと、振りかえった。
「なに、ついてこいって?」
犬は歩きだすと、また立ち止まった。
「だめよ、人を探してるから。会うまで帰れないの」
網船磯には、登るのに大人でも苦労する大きさの屏風岩がそこらにあって、子供たちの格好の遊び場となっている。
なかでも最大のものが《展望岩》と呼ばれていた。
高さ約二十メートル、長方形の上に正方形を重ねたような形をしている。

犬が〝早くこい〝というように吠えた。
「ダメ、つぎは展望岩にのぼって遠くまでみてみるの」
江利は北東方向にある展望岩を目指し、屏風岩をこえていった。
ついてこないとみると犬は、江利のうしろをついてきた。
潮にひたるきわでは、滑らないよう足の底すべてに等しく力をかけねばならない。
腕をゆるく伸ばし、腰だめにかまえ、重心を低くとって移動するのがコツだ。
網船の子であれば誰でもできる歩き方で、何度も滑るうち自然と身につく。
一メートルほどの幅の広いたまりがあって、江利は助走をつけて跳んだ。
着地で踏んだ岩が動き、バランスを崩し、片方の足が膝まで水につかる。
「ああ、くそっ」
母親の怒る顔がまた浮かんだ。
よく見れば、踏んだのは加工された岩だった。
太平洋戦争時、東京湾の入り口にある網船磯は、大日本海軍の主要な防衛拠点、駐屯地だった。
ここで米軍を食い止めねば、東京湾に侵入され、首都まで一直線だ。
何層ものバリケードに似た、独特の形状である屏風岩は、守るにうってつけの地形だった。
磯には小舟を通す水路、中型の軍艦も入港できる隠し港が造られた。
戦局が進めば、潜水艦も配備されるはずで、軍船の造船所も建造予定だった。

海漁町網船区の隣の区ー戸立区だけは唯一手つかずで、屏風岩は国定記念物に指定されているが、そこをのぞいて、広大な磯の全域に軍の仕掛けがほどこされた。
また当時の名残である軍の遺物は、町中や山中にも存在している。
たとえば無数の防空壕だ。
戦後になって、国の役人や民間の歴史研究家が幾度となく調査におとずれたが、あまりの数の多さに把握を断念、危険な穴のいくつかをコンクリートで塞ぐ程度に処置はとどまっていた。
無用の長物と化した避難壕も、網船小の児童たちからすれば“ドキドキする、面白い、変な穴っぽこ”といったところだが、崩落の危険があり、野生動物の棲家にもなりやすい。
学校は、立ち入り禁止と、児童たちに言い渡していた。

(もしかしたらインチョーは、防空壕にいるのかな)と考えるうちに、江利は展望岩の下についた。
角度がきつく、頂上は見えない。
犬がすこし離れた場所で舌をだしていた。
「なによ、やめろっていうの? おまえがのぼれないからでしょう」
江利は岩に手をかけた。
(男の子たちはみんな登ってる。大丈夫。気をつければ危なくない)
最初が肝心だと聞いていた。
右足を、腰より上にある岩のでっぱりに引っかけ、地面を蹴って、思いきり頭の上に左手を伸ばす。
(とどいた!)
頭上にある岩をつかんだ。そのまま懸垂をするように体を引きあげる。
肩と腕の筋肉が熱くなり、痛くて、離してしまいそうになる。
だがここさえクリアすれば、頂上まではたいしたことはないらしい。男の子たちがそう話していた。
岩は冷たく、手の平が痛んだ。
腕と足に力をこめ、なんとか岩場に乗った。
あおむけになり、激しく息をつく。
手のひらをすりむき、服も汚れてしまった。
江利は、火傷した痕の残る手のひらをはたいた。
二歳のときに、コンロにかかっていたやかんを誤って倒したときの傷だ。
男の子たちの話は本当で、あとはアスレチックを登るより簡単だった。
二分とかからずに頂上へ着いた。
てっぺんに立つと、春特有の勢いのある風が吹きつけた。
ずっと先まで見えた。だいぶ先まで潮が引いている。
大きな波が岩にぶつかって砕け、真珠のような泡を何度も空中にまいた。
沖にタンカー船が四隻、動いていないように見えるほどゆっくり帆走っている。
高所で強さを増した風が火照った体に気持ち良かった。
伸びをすると、汗に濡れた腋がひやりとした。
江利は頂上を時計回りに、四方を探した。狭い網船区のすべてが望める。
北には、校歌に歌われる《奥名山》が堂々とそびえている。
山全体が鮮やかな緑で、山の両肩から視界いっぱいまで稜線が伸びていた。まるで大きな城壁だ。
海と山のあいだの狭い土地に、畑や田んぼ、それに森、あとはまばらに家が建っている。ちらほらと人の影が見えた。
やはりここは、山と海に囲まれた狭い土地だと江利は思った。
江利は磯をもう一度探そうと縁に近づいた。
高い場所から真下をみおろすと、体が浮遊したような錯覚につつまれた。

下方に何かが見えた。
その瞬間、下から突風が吹きつけた。
江利は崖下に落ちそうになり、叫び声をあげて、しゃがみこんだ。
心臓が激しく打ち、冷や汗をかいた。
『脳みそはプリンくらいの柔らかさだ。ノウショーという液体に浮いてるんだ』
理科の水やりドクロの話を思いだした。
あの先生は、いつも気持ち悪い話ばかりする。
空中に泳ぎだし、頭から地面に落ちて、プリン色の脳みそが飛び散る姿を想像し、江利は気分が悪くなった。
目眩がおさまると、今度は四つん這いで崖の縁へ寄り、頭だけをのぞかせた。
すこし離れた場所に、異様なものがある。正方形に近い穴だ。
家が三、四軒もすっぽり入るほど大きい。
《廃穴》だ。
穴といっても、海水が満ちている。
海軍が造った人工物の中でもひときわ巨大で、周囲の自然から浮いている。
地上に黒い穴が空いたようで不気味だった。
岸に近いにもかかわらず、けたはずれに深く、底がうかがい知れない。
なんの為に造られたのか、誰にも用途はわからないそうで、絶対に近寄ってはいけないと学校で言われている穴だ。
海と接していないのに水をたたえているのは、とても深いところでつながってるからだそうだ。
江利は目をこらスト、さっき見えたものがいないか探した。
波が立たないはずの廃穴の水面が、大きく揺れている。波が寄せ、穴のまわりの岩が濡れていた。
さきほど、一瞬だったが大きな何かが廃穴に沈んでいった。
潮がひくように興奮が冷めていき、江利は、夢から覚めて現実にもどったような気がした。
(何かの生き物? でもあんな大きな生き物って)
圧力を感じたほどの巨大さ。
急に、独りでいることが心細くなった。
しばらく見ているうちに、水面は静かになった。
(とにかく降りよう)
そして早く家に帰ろうと江利は決めた。
頑固な江利がそう思ったほど、不気味な何かだった。
・目次『六年生のあゆみ』