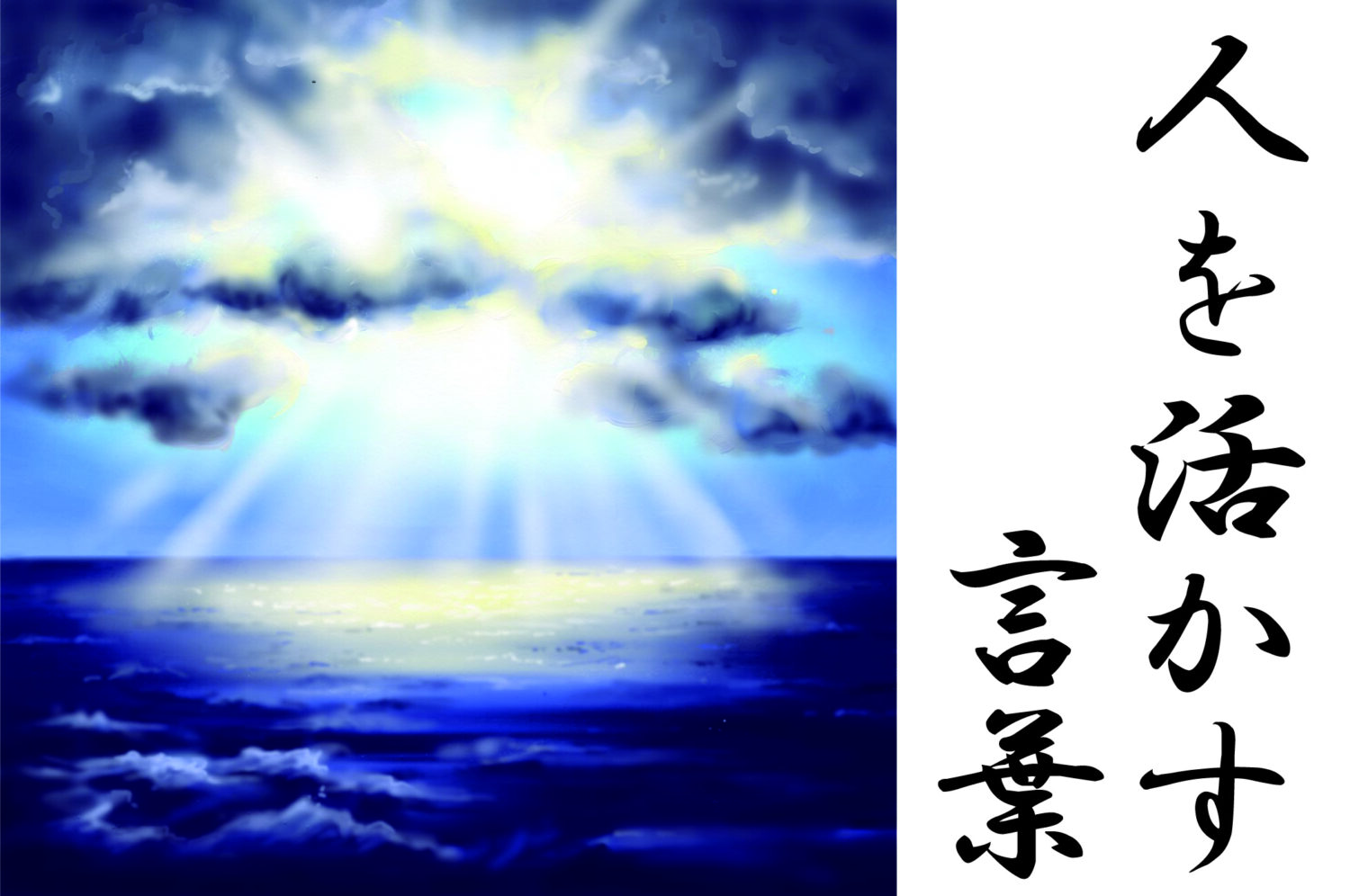少年と怪物
四月
茶ん爺3 〜おれは物乞いじゃない〜
はげしい風に身をゆだねながらインチョーは、はじめてその自転車、チャレンジャーと会ったときのことをはっきりと思いだす。
黒くて太い、自転車の怪物。
でかすぎるライトが、まるで目玉のように、にらみつけてきた。

茶ん爺が言った。
「自転車ぐれえ、みんなもってんだろう? オメエにやる。大事にしろや」
茶ん爺がどこかからもってきたその自転車を、インチョーはひとめで気にいった。
三年生の春のこと。まだ〔失われた世界〕ができる前だ。
同級生はみんな、一年生になると自前の自転車を買ってもらえる。
だから、たまにみんなと遊ぶと、インチョーは彼らの自転車のあとを、全力で走って追いかけることになった。
そのみじめな気もちったら、言いあらわしようがない。
でも母が乗っている軽自動車は、廃品同然だ。
母の服もまた、インチョーがおぼえているかぎり一着もふえていない。
だから、自転車を買ってほしいと、どうしても言いだせなかった。
だから、茶ん爺が自転車をくれたときは、大喜びするだけで、ただただ嬉しくて、母がなんと言うか、そんなこと考えもしなかった。
自転車を持って帰ると、母はインチョーの頬をぶんなぐった。
「物乞いなんてするんじゃない!」
「乞食にそだてたんじゃない!」
なにがそれほど母の怒りにふれたのか、まったくわからない。
しかし母が、怒鳴りながら、何度もひっぱたいてくる。
肩をつかんではバチン。髪をつかんではバチン。
バチン! ビチン! バヂン!
ほほがパンパンに腫れて、白熱電球さながらに熱かった。
インチョーは泣きじゃくってあやまった。
だが母はとまらなかった。そのうちに、母も泣きだした。泣きながらインチョーをなぐった。
六年生になった今でこそ、こうした、ときおりの母の激しい怒りは、なりをひそめたが、インチョーが四年生くらいになるまで、母はたまにこうして怒りを爆発させた。
ただ、母の怒りは、息子である自分に対してではなく、でていった父さんとか、世の中に対してとか、そういったものなのかなと、今では、なんとなくそう思っている。
小学校三年、九才のインチョーは、しゃくりあげながら、自転車について必死に説明した。
血のにじむ唇をふるわせ、単語ばかりをつづけて話す息子の話を、母はようやくきいた。
(母さんはちゃんと話をきいてくれるんだ)
インチョーの記憶に、そのすがたは強くきざまれた。
盗んだんじゃないよ。茶ん爺さんにもらったんだよ。
インチョーは嗚咽しながら、何度も、何度もくりかえした。
母は「……つかれた」と言って、深いため息をついた。
そしてひと言。
「明日、その人のところへ返してらっしゃい」
インチョーはもちろんうなずいた。
父親はいない。この世界のすべては母だから。
翌日、ほっぺたと目をはらしたインチョーは、死人のような顔で茶ん爺の元へいった。
もちろん自転車に乗ったりしなかった。押していった。
母が『あなたのものじゃない。絶対につかってはだめ』と言ったから。
茶ん爺は、インチョーのミミズばれや青タンだらけの顔を見ると、片眉をあげた。
何事にも動じない茶ん爺にしては、めずらしい顔だった。
インチョーが涙をこらえながら、母親との話をすると、茶ん爺はおおいに気分をわるくしたようで、手荒くつっぱねた。
「それはもう、わらにやったもんだ! おんのではねえど!」
風の荒れた日、波の高い日でも、はっきりと言葉を伝えなくては命があぶないことがある漁師特有の、怒っているような調子の大声で茶ん爺は言った。
「それによ、そんな軽い気持ちでやったんでねえ」
「……うれしいんだけど……茶ん爺、本当にうれしいんだけど……どうしてももらえないんだ」
うちひしがれてうつむくと、茶ん爺はそっぽをむいた。
「……大事なモンだかん。わらに乗ってもらいたかったんだけんな」とボソッと言って、悲しそうな顔をして、漁師小屋にひっこんでしまった。
インチョーは、その自転車を、茶ん爺の漁師小屋の前にとめて、帰った。
その晩、電話があった。
母は、だれかと長いこと話していた。
電話がおわると、母は卓袱台で頭をかかえた。
母は長いこと、眠る前までそうしていた。
次の朝、朝食を食べおわって、
「そこに座って……正座しなさい」母が言った。
正座した母と、ちゃぶ台をはさんでインチョーは座った。
「……もらわないんだったら捨てるって言ってたわ」母はため息まじりに言った。
母は長いこと沈黙したあとで、
「ちゃんとお礼を言ってくるのよ……いっぱい。いっぱいお礼を言ってきなさい」と言った。
インチョーは家をとびだすと、スキップどころか、バネのおもちゃみたいに、とびはねながら茶ん爺の漁師小屋のある米仲港へ全力で走った。

来ることを知っていたのだろう、茶ん爺が小屋の前に立っていた。
茶ん爺は、自転車のサドルを分厚い手のひらでポンポンとたたくと、にんまりした。
しわくちゃの顔が、ほとんどしわだけになった。
「こいつに名前をつけてやらにゃいかんぞ、泣き虫坊ん主。こいつにゃ、こころがあんだ」
実際のところ、その自転車にはこころがあった。
「茶ん爺4 〜 港町 〜」につづく
・目次「六年生のあゆみ」