「忘れられない話 2」
飽きのくるペースが早まった気がしないでもないが、30回をむかえ、今回は経営ではなく物書きの話をしたい。
ある出版社の現担当はOさんという男性なのだが、
このO編集さんがとても優秀な方で、大御所も担当されている。
そのおひとりが、故・山崎豊子先生だった。
山崎先生の著作は、映画、ドラマなどに数多くなっているので、筆名を知らなくても、
『白い巨塔』、『沈まぬ太陽』、『不毛地帯』、『華麗なる一族』、『山河燃ゆ』
などと挙げれば、聞いたことがあるというかたも多いだろう。
わたし自身は、山崎先生にお会いしたことはないが、
徹底した取材姿勢はうかがっていたし、
足をつかった調査を骨芯におくそのスタイルは素晴らしいと思っていた。

話はもどるが、
あるとき編集者Oさんと打ち合わせをしていて、
意見がくいちがった。
よくあることだが、いわゆる書き直しというやつである。
あるシーンについて、わたしは書き直す必要はないと思い、
O編集さんは、書き直して欲しいと考えている。
(物書きは、作品をわが子と思っているから、書き直しはたいがい、机をぶん殴りたいほど業腹である。
また不出来な子どもであっても、いや、不出来だからこそたいへんかわいいものだ)
また不出来な子どもであっても、いや、不出来だからこそたいへんかわいいものだ)

(※写真は打ち合わせのイメージ)
話は平行線をたどったのだが、
Oさんが、ふと山崎先生の話をはじめた。
O「伸さん、山崎先生の最後の作品は『約束の海』というんですが、
これが未完でお亡くなりになられました」
伸「もちろん知ってますよ」
O「じつは紙上で連載になっていたころを担当していたのが、わたしでして、
先生は、ベッドのうえで、亡くなる直前までペンを握っていらっしゃいました」
伸「そうですか。作家の鑑だと思います。わたしもそうありたいですね」
O「わたしは、新人のころから山崎先生にお世話になっているんですが、はじめて山崎先生から原稿をいただいた際、感想を求められたんです」
伸「へえ。大変だったでしょう」
O「大御所のかたには、編集といえどやはり言いたいことが言えないんです。
まして新人の編集であれば、褒めるしかできない。
それで褒めまくったのですが、ひと言、山崎先生が『それはあなたの意見じゃないよね』とズバッとおっしゃいまして」
伸「へえ」
O「それでおそるおそるわたしは、
『恋愛のシーンが古くさいと思いました』
と大汗をかきながら言ったんです」
伸「よくいいましたね!」
O「そしたら先生が、一瞬鬼のような顔になりまして、、、、
でもそれが一瞬で沈んで、
『ありがとう。わたしもそう思ってたの。書き直すわ』って、にっこりされたんです」
さすが名編集者である。
ぐうの音も出なかった。

たとえどのような立場になっても、山崎先生は新人編集者がいうことにだって、
自分の作品を高めるヒントがあるのではないかという、そのわずかな可能性を、
けっして無視しなかったという話だ。
ひよっこのわたしが書き直しを承知したのはいうまでもない。
おおいに我が姿勢のありかたを反省した日であった。

上記は文壇の話であるが、こうした姿勢は、どのような業界にも共通していると思う。
えらくなったとしても、歳をとったとしても、
人の意見に耳をかたむけられる度量があるかどうか、
これは大きなちがいとなり、器や腕となってあらわれてくる。
専門家になればなるほど、ひとの意見をきけなくなる。
これをもって初心者には可能性があり、専門家には可能性が無いというのだと思う。


(初心者と専門家)
このあたりは、そのうち「禅」について書く時にまたふれようと思う。
初心、ビギナーズマインドの重要性などだ。
よく言われることだが、「きく」という言葉には大別して三種類ある。
これを紹介して、シメとしたい。
「聞く」→ 音、話など、一般的に聞くこと
「訊く」→おもに「たずねる」こと
このふたつが意図せずできると言われており、
のこる「聴く」が、無意識ではできない。
「聴く」は、人民の声を聴く、名曲を聴く、身の上話を聴くなどに使い、
ただ単に音をとらえるのではなく、
自分の気持ちや姿勢が問われる。

山崎先生のように、いくつになっても
「聴ける」耳をもっていたいと思う。
そうして可能性をつぶさずにいたいと思う。
╋━━━━━━━━━━━━━━╋
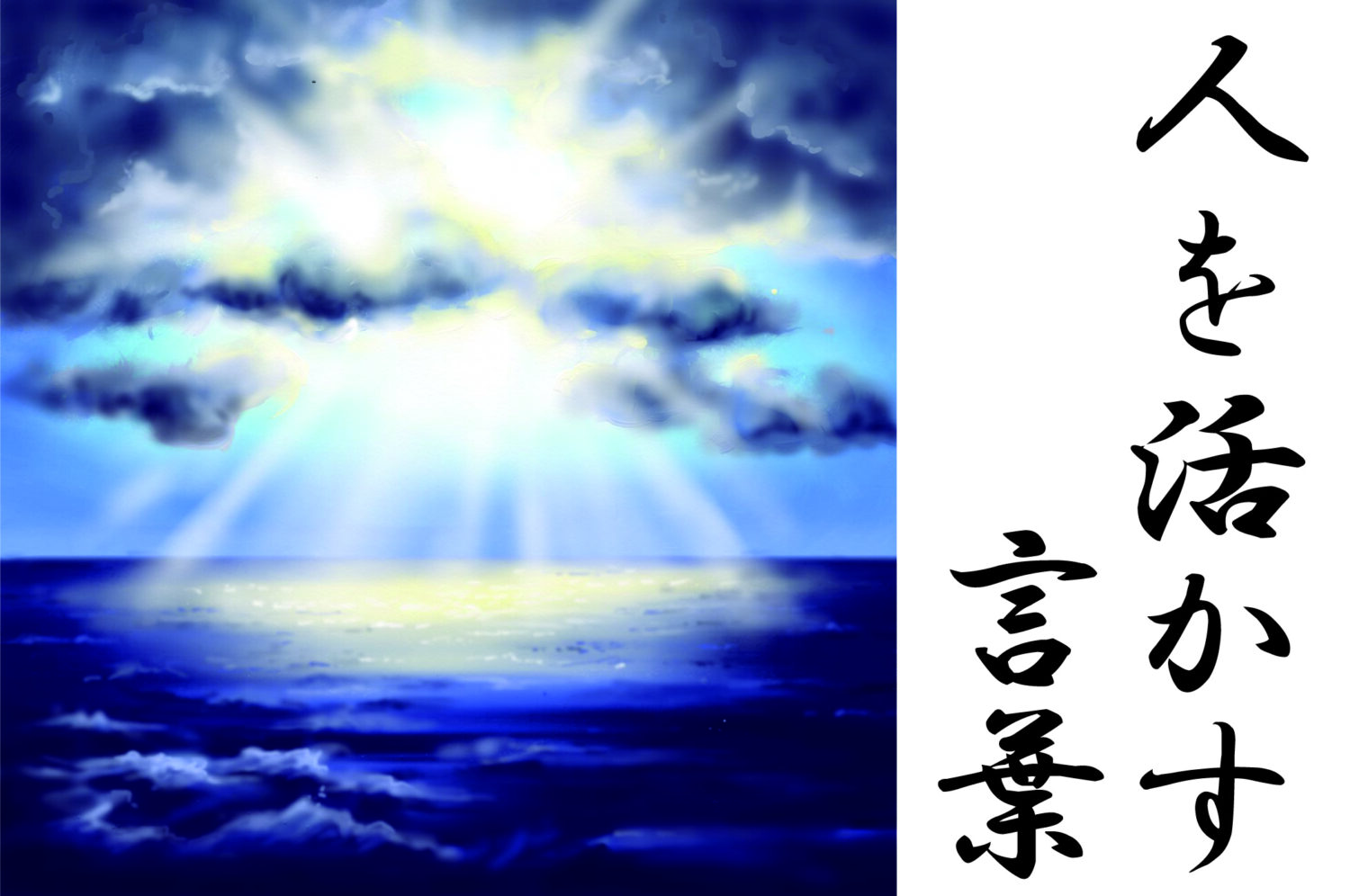



コメント