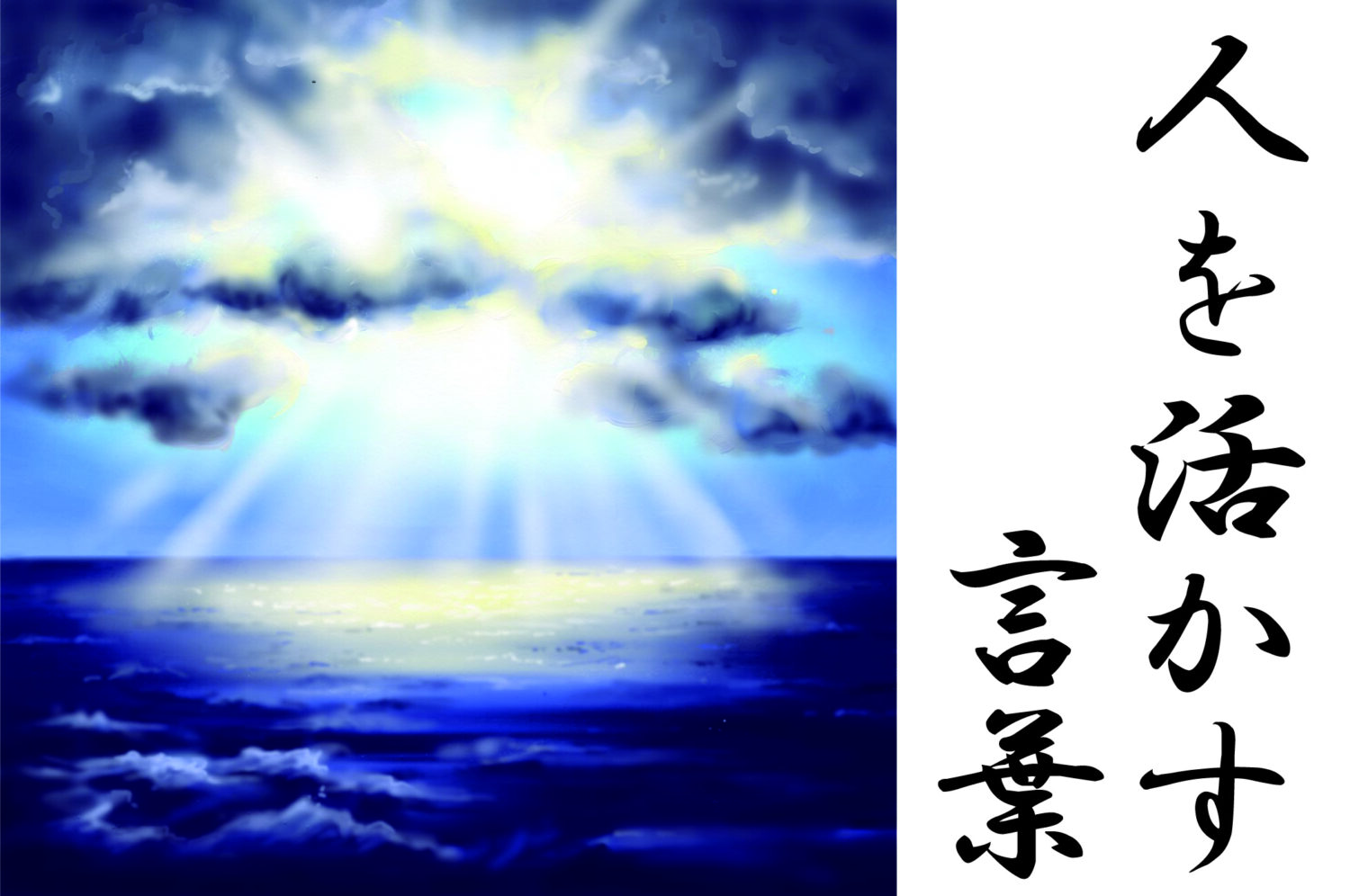少年と怪物
四月
遭遇3 〜それ〜
およそ十分後。
廃穴の横手にある、盛りあがった岩の上に江利は立っていた。
九割がた帰ろうと思っていたが、もう一度だけ、はっきり見たかった。
ちょっとでいい、展望岩の上から見えたあれ。
深呼吸し、シュッシュっと鼻から細かく息を吐く。
“落ちつきたいときにやるのよ”
そう母親に教わった方法だ。
なにがあってもすぐに駆けだせるよう、油断なく身構える。
もっと近い場所で見たかったが、ここまでだと考えた。
もしも、あの大きい何かが本当に生き物だとすれば、これくらいの高さが無ければならない。
(あれがなんだかわかれば、インチョーのグループに入れてもらえるかもしれない)
江利はそう思った。
『ジョーズ』にでてきた恐ろしいホホジロザメの背びれそっくりの、三角形の尖った岩に手をかけ、江利は、廃穴の水面をうかがった。
湖のように平らだった。
廃穴は深いが、もし落ちたとしても泳ぐ自信はあった。
こちら側は急斜面なのであがれないが、反対側まで泳げばいいだけのこと。
目算で学校のプールの倍くらい。
この距離が泳げない人は、網船ではアホあつかいされる。
突然、背後で犬が吠えた。
「静かにして! わたしがここにいるってわかっちゃう……」江利は振りむき、言葉をのんだ。
犬の横に、不思議な幅広い線がある。
展望岩から眺めたときは気づかなかった。
幅五メートルほどの帯のような赤い跡が、海から廃穴までつながっている。
帯は、江利の立っている場所より大きな岩や起伏をなんなく越えていた。
まるで地形に関係なく引かれた線路のようだった。
(……こんな風にまっすぐ)
逃げるという思考が手足にとどくまえに、廃穴の水面が爆発するように噴きあげた。
水しぶきが雨のように降り、一帯が白く染まる。
江利は悲鳴をあげて頭をかばった。

なにかが江利の両足に絡みつき、一気に引っ張った。
足をすくわれ、江利は倒れこんだ。
鋭利な岩の先端が、肩甲骨の下あたりに刺さった。
肺の空気が塊となって喉を抜ける。
シャツの背中側に血が滲み、すぐにも岩を濡らした。
江利は大きく息を吸い、叫んだ。
足をつかんでいる何かが、江利の体を激しく左右に振った。
江利は、背中にはしった激痛で一瞬白目をむいた。
犬の激しい吠え声が、すぐ近くのはずなのにとても遠く聞こえる。
背中に刺さる岩が、魚の口に引っかかる釣り針のようになり、江利は引きずり込まれずにすんでいた。
苛立ったように何かが江利の体を前後に振り、つぎに上方へ引っ張った。
背中から岩が抜け、江利はなすすべなく、廃穴に落ちた。
冷たい海水に包まれ、全身の毛穴がすぼまった気がした。
江利は激しくもがいた。
何かが足首に巻きついたままだ。
目を開くが、塩辛い海水が目にしみ、太陽をまともに見つめたようだった。
輝く細かい泡が水面に昇っていく。

海水が傷口を洗い、白熱するほどの痛みがはしり、江利はあやうく叫び声をあげそうになったが、必死でこらえた。
(息を吐いちゃいけない! 吐いたら吸わなきゃいけなくなる!)
網船小で習う、溺れたときの教えが浮かんだ。
『息を吸って止めれば、それだけ考える時間が増えます。溺れたときはとにかく息を止めて水面にでましょう』先生はそう言っていた。
苦しくても息は飲みこむ。それが助かるコツだと。
江利は、足に巻きつく何かを、思いきり両手で引っ掻いた。
ぬるりとした感触、そして鋭い何か。
爪が七枚も剥がれたが、痛みは感じなかった。だが、何かは離れなかった。
白い肉のヒモを伸ばした桜色の爪が海中をただよう。
(苦しい)
(苦しい)
(苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい……)
(息を吸わなきゃ)
(息を吸わなきゃ)
激しい動きで余計に苦しくなり、頭が沸騰したようになった。
なにを考えているかわからなくなった。
(空気)
(空気、空気、空気、空気、空気、空気、空気……)
空気のことしか考えられなくなった。
(くうき)
(くうきくうきくうきをすわなきゃくうきがはやくはやくにげてくうきをすわないと)
水底の暗闇から、なにかが浮かびあがってきた。

江利はそれをみると、息を止めることを忘れ、わずかな空気とともに絶叫した。
不意に足の呪縛が解けた。
江利は水面へ泳いだ。
習い覚えた泳ぎなど消えていた。原始的に水をかき、水をけった。
頭が水面を割り、音をたてて息を吸った。
冷たい空気が喉をとおり、肺へくだる。
酸欠で頭全体がどくどくと脈を打ち、視界が点滅し、意識が遠のいた。
江利は朦朧としながら、岸へむかって泳ぎだした。
まるで糊の中を泳いでいるようだった。
すこしでも気を緩めると、沈んでしまいそうになった。
あと五メートル。
背後で水音がした。
江利は振り返り、悲鳴をあげようとして水を飲み、それを吐き、泣いた。

あと三メートル。
江利は鼻水を流し、泣きながら泳いだ。
小便をもらし、腰のまわりの水が黄色く変わる。
背後で巨大なそれが身じろぎし、大きな波が江利を揺らした。

あと一メートル。
江利は頭の後ろに、象ほども大きな気配を感じた。
江利は悲鳴をあげながら、岸に手をのばした。
へりをつかみ、一気に体を引きあげる。
そのまま転がって、すこしでも水から離れる。
腰が抜けて立ちあがれず、江利は這いながら逃げた。
背後で、大量の空気が吸いこまれる音がした。
ついで、鼓膜を破るほどの咆哮が轟いた。
何百という金属を打ち鳴らしたような、断続的な音だった。
這っていく江利の目の前の水たまりに、無数の小さな水滴が油のように跳ねた。

逃げる江利の瞳に奥名山がうつった。
(ママ……家……帰り……なんで……)
(死にたく……ごめ……言いつけ……わたしが……わる)
江利は怪物にひき潰された。
右手はちぎれ、脇腹と腰の横、太ももから血に染まった骨が突きでた。
生木を折るような、柔らかな音が重なる。
重機にでも轢かれたようだった。
怪物は江利の首を切断すると、高々と宙に飛ばした。
怪物は、首のない江利の体を牽き、深い水底へもどっていった。
「帰らぬ子 〜母の直感〜」へつづく
・目次 「六年生のあゆみ」