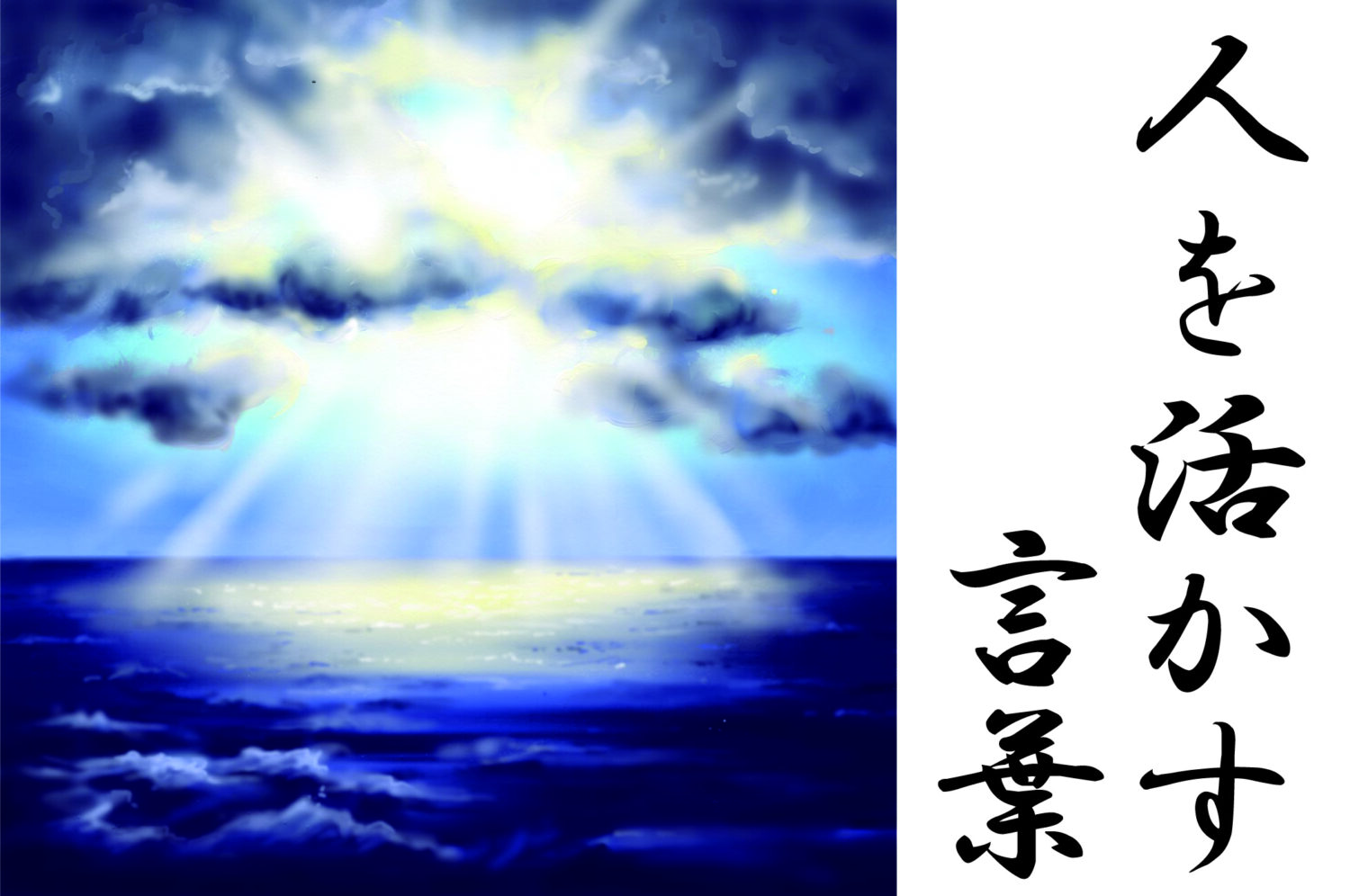少年と怪物
四月
飛行体験
※表紙画像 photo by Colin Behrens
【二時間後 十一時五十五分 相原江利】
江利は、二時間前とおなじ曇り空を見ていた。
先ほどと違うのは、目の伝える現在の情報と、脳が映しだす昔の記憶と、意識がそれらを行き来していることだった。
江利は上空、十五メートルほどを飛んでいた。
体は失い、首だけだった。
三つ編みは切断されて髪はざんばらになり、首の切り口から鮮血を凧糸のように引いている。首は、数秒前に切断されたばかりだ。
江利は、欧米の詩人が好んで使う表現―タイムスポットと呼ばれる境地にあった。
永遠を一瞬に、一瞬を永遠に感じる状態であり、日本語では走馬灯といった。
空高く放物線を描く江利は、空を、太平洋を、奥名山を見ながら、その刹那の隙間に、一生を追体験していた。切れ切れに。
古いトースターで、食パンが焼けるのを待つ父親の背中が見えた。
パンの焼ける香ばしい匂いがした。
「こぐんだ! しっかりハンドルを持って!」
父親の声が背中にあたった。
角砂森の外れにある公園で、江利は汗ばんだ手の平でふらつく自転車のハンドルをぎゅっと握る。
だが途端にぐらりと大きく揺れ、地面に倒れこんだ。

富士山の近くにある湖でモーターボートに乗っている。
パパとママが嬉しそうな顔をしている。江利も笑う。
ママの帽子が強い風に吹かれて飛んでいき、ママが悲鳴をあげた。

信じられぬほどたくさんの記憶が流れて、消えていく。
それらは二度と戻らない。
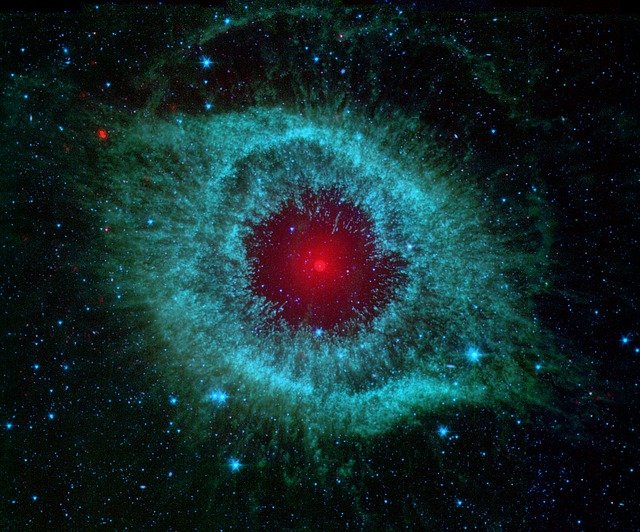
江利は瞬きした。切断から十秒足らず、江利はまだ生きていた。
涙と鼻水が、目と口の端を後方に流れた。
力の作用で、景色が下回りに回転していく。
視界、眼下の磯が反転していく。
先ほどまで一緒に遊んでいた野良犬が走っている。
吠えているが、不思議なことに声がまったく聞こえない。
景色が回っていき、飛んできた方向へ向いた。
そこに、あの、恐ろしいものがいた。
江利は叫んだ。
だが声はでず、口が大きくあいただけだった。
岩に激突するまで残り二秒の飛行中、江利はさらに三度タイムスポットに入った。
ひとつめは、世界の終わりを願う少年との出会い。
八ヶ月前の七月のこと。夏休み直前だった。
「不思議なふたり」につづく
・目次 「六年生のあゆみ」