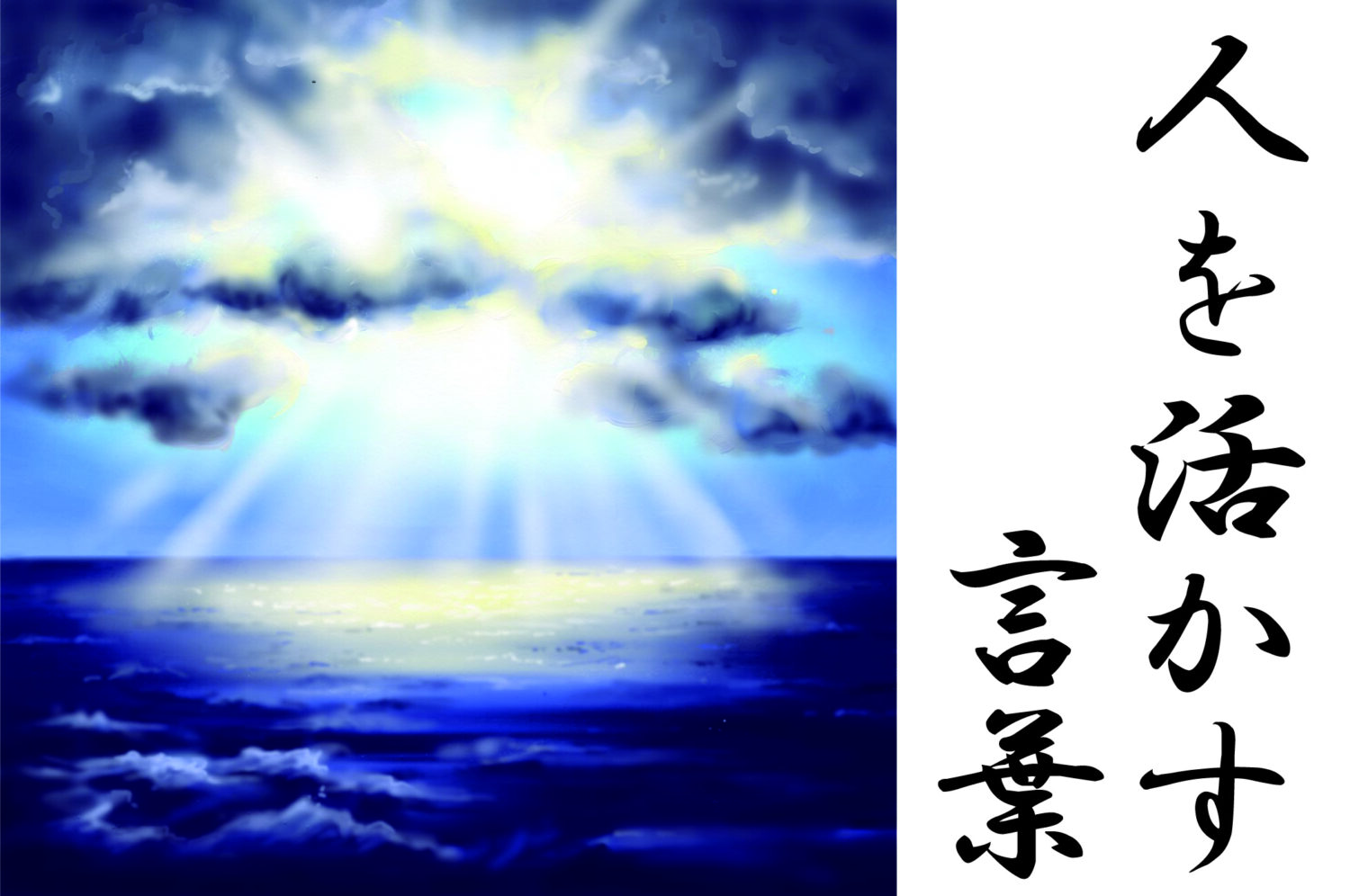少年と怪物
四月
寄り添えの木2 〜白と黒と黄色〜
「なんでアメリカ軍は、よりぞえの木を燃やそうとしたの? 別に普通の木じゃん。さとじいは、アメリカが戦争に勝った後のことだって言ってたけど」長治がハカセにたずねた。
それは三ヶ月ほどまえの夜、インチョーが夕飯を食べながら母親に聞いたのと、まったくおなじ質問だった。
「まあ憂さ晴らしとか、単純な憎しみとか、色々あるわよ」
母がコップの水を飲み、そう言った。
「日本とちがって、基本的に、物には魂が宿らないって思ってるのもあるし。キリスト教の影響でしょうけど、魂は人間にしかないって考えるの。原理主義ってわかる?」

「げんりしゅぎ?」インチョーは皿の上の、キャベツの千切りにソースをかけた。
「まあ、神話そのものを元に考えるというか、極端な考えのことよ。たとえば、黒人は土のかたまりから生まれたって本気で信じたり、あたしたち黄色人種もサルが進化したもので、これも動物だから魂がないって信じたりね。世界にはまだまだかなりの数、そうした考えの人っているのよ」
「なにそれ? 人間は猿から進化したのに、なんで肌の色で、土とか猿とか、おなじ人間なのに変だよ。じゃあ白人は何から生まれたの? ぶた?」
「白人は、神のつかわした人間」

「ぜんぜんわかんない。アメリカ人はどうしてそんな風に考えるの?」
「アメリカ人というわけじゃないわ。キリスト教というか、アングロサクソンていう白人種には、そう思う人もいるってこと。ほら、日本にだってそういう人はいるでしょ? 神に守られた国だから、絶対に戦争に勝てるって、そう思った人たちよ」
「ああ、それなら歴史で習った。でもそうしたら、ますますよくわからない。よりぞえの木がただの木だって思うなら、燃やさなくていいのに」
「日本人は、だいたい木とか、この茶碗にだって、百年もたったら何かが宿るって考えるじゃない? 付喪神ってあんた知ってる? かあさんはそういう考え好きよ。畏敬って言葉は習った?」

「知らない。食べるもの残したら目がつぶれるってこと?」
「そう。そのグリーンピース残したらそうなるわ」
インチョーは手つかずの、噛むと鼻水そっくり液体が出る緑色の球体をながめた。
「日本は戦争に負けたわよね。勝った方は復讐したくなるのよ。日本人も一緒だけどね。中には家族を殺された人もいるし。勝った側の権利、うーん。自由って言ったらいいかしら。とにかく人間はそういう事をするのよ。水に流せないの。徹底的に反抗させる気をなくさせるのもあるし」
「復讐ってやめられないの?」
「あんた、アタシを殺した人がそのあたりを歩いてたらどうする? 笑顔で」
「ああ、なるほど」
「当然でもあるけど、もちろん愚かな事よ。どっちかが死ぬまで戦って、決着をつける。勝った方が負けた方を許すのはできない相談。負けた方もおなじ。その繰り返し」
「じゃあ、最初から戦争しなきゃいいのに」
「人間にそれができれば、世界はすごく変わるでしょうね」
母はそう締めくくった。

「寄り添えって名前になったのは、関東大震災の時だって、里じいは言ってたよ」ハカセが言って、インチョーは物思いからさめた。
「関東大震災が起きたときは、ちょうどお昼で、どこも料理の真っ最中だったんだ。それに、今みたいにガスじゃなくて、カマドで火をおこしてるところがほとんどだった」
「大地は傾き、家も人も、風呂もカマドも、あっちの地平線からこっちの地平線まで転げるように揺れ!」
マウスが叫び、激しくジェスチャーで表現した。
「建物はどんどん倒れ、またたくまに、地獄のような炎が燃え広がった。木の家は十割! まさに燃えまくった!」

「深夜だったら、あんなに被害は大きくなかったって、さとじいは寂しそうに言ってたでしょ」なおも止まらないマウスへ、ハカセが苦笑いをしながら言った。
「さとじいの生まれた家もこの近くにあって、やっぱり火事で燃えちゃったって」長治が言った。
「お、そこだけはオレも覚えてっぞ」ダイが言った。「あれだろ、すげえ火の中を家族みんなで逃げたって話だろ? どこをどう逃げたかの、気がつけばよりぞえの木にくっついて、村が燃えるのを見てたって」
「いっつも寝てんのに、そこだけ覚えてんだ」マウスがぱたっと身ぶり手ぶりをやめた。
「だってよ、さとじい泣いてたろ。そりゃ覚えてるわ」
「よりぞえの木が不思議な力をだしてくれたって言ってたね」長治が言った。「みんなを安心させて、火の粉をよせつけなかったって」
「そのうちに村のみんながどんどん避難してきたんだ」ハカセが言った。「寄りぞえという名前は、私がつけたんだって、さとじい、いつも自慢してたね」
「五十年間くらい、ずっと同じ話してんだろうな」ダイが皮肉とも、思い出深いとも、どちらでもあるように言った。
今年から図工の授業は、教頭の赤城先生―水やりドクロが教える。寄り添えの木の話を語る人はもういない。
(この木の名前も、いつか忘れられてしまうのか)インチョーはふと思った。
もし呪いというものがあるならば、それもまたいつか変わったり、消えてくれるものだろうか。そうも思った。
インチョーは、いまはもう他の場所と見分けのつかない、だが自分には、はっきりと見分けのつく、木の根元の一部をみた。
インチョー には、そこから黒ずんだ霧のようなものが立ちのぼっているように感じた。
メンバーにどれほど呼ばれようとも、あれ以外、インチョー はよりぞえの木にけっして近よらなくなった。

「弓事件」につづく
・目次 六年生のあゆみ