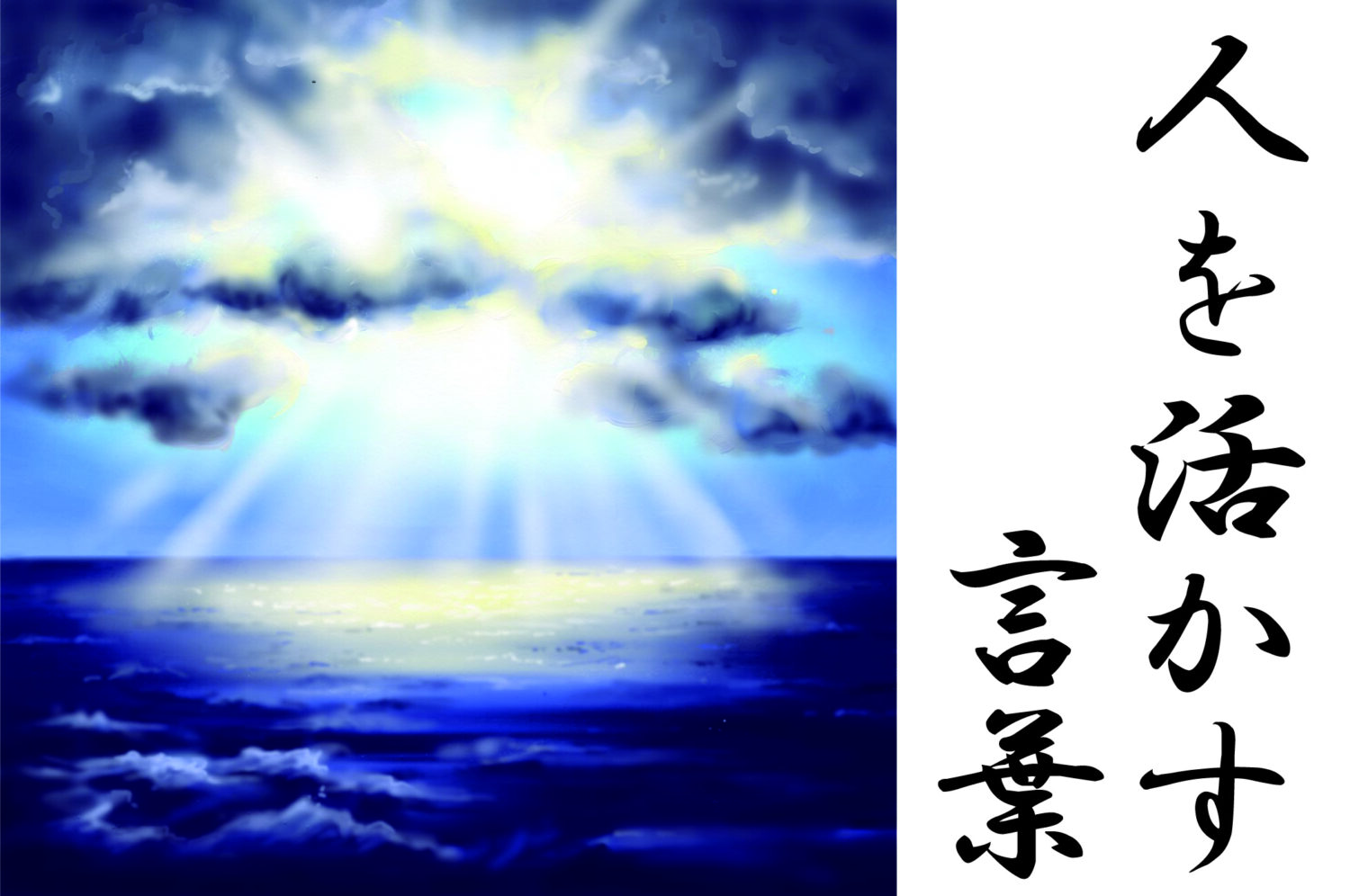少年と怪物
四月
初恋2 〜 小町光〜
「ねえ、聞こえてる?」女の子が言った。
インチョーは、非難めいたその声で我に返った。
「いや、あの、何にもついてない……ごめん、じろじろ見て……その、ちょっと考えごとしてたんだ……はじめまして」
インチョーは切れかけの電球のように、目をパチパチさせながらしどろもどろに言った。
自分が、なにをしゃべってるかもわかっていなかった。
(すごくキレイな目だ……まつげが長い……キラキラしてて、目薬をさしたばっかりみたいだ……なんでこんなに唇の色が濃いんだ? 赤い絵の具をつけてるのか?)
「そう、ならいいんだけど」
女の子が怒ったように言って、荷物を片付けはじめた。
インチョーは机がくっついていることを、六年間ではじめて意識した。
(おい、みんな大変だ。この子の机とおれの机、くっついてるぞ)
「あんまり前じゃなくてよかったわよね」
「え? ああ……まあ……そうかな」
「あなた、インチョーくんて言うんでしょ?」
インチョーは、名前を知られているだけでなぜこんなに嬉しいんだと思いながら、馬鹿になったみたいにうなずいた。
「私、こないだの冬に引っ越してきたの」
なぜこの子が初めて見る顔なのか、それでわかった。
六年生は二クラスあるとはいえ、全員で七十人ちょっと。
全員がこの狭い網船四区の子で、顔ぶれも一年生から変わらない。全員が全員を知っている。
三ヶ月ほど前の冬休み、秘密基地でメンバーが話していた事を、いまさらながらにインチョーは思い出した。

『すごくカワイイ子が、都会から転校してきた!』という話だった。
その子は五年二組に入り(インチョーは五年一組だった)、二組だったマウスとハカセが、いかにかわいいかを熱く語りあっていた。
『マジで足し算なんだ! 笑うともっと美人なの! もうすんげえの!』とマウスが言っていた。
インチョーはそのとき、小学校の終わりまでに防空壕を完全に回りきれるかどうかをダイと考えていて、聞き流していた。
あの話が今、現実となって隣にいる。
インチョーは、落ち着こう、冷静になろうと口をつぐむと、いつものように相手が何を考えているか、何を伝えたいのか、相手の目をしっかりと《見》て、表情や体の動きからも読みとろうとした。
だが、どうしたことか。女の子の目を見たとたん、水中に放りこまれたように息がとまった。
表情を観察するなど、賽銭箱にツバ吐くほど無礼な真似に思えたし、しぐさを見ることも、世界一はずかしいことをしているように思えた。

つまるところ、インチョーの目はおろおろと、机の上や教室をさまよい、女の子については肩のあたりをときおり見るにとどまった。
(変だ……なんだかうまく考えられない……なにかが変だ。おかしい)
五年生のとき、六年生三人を相手に一人でケンカしたが、まったく怖さなど感じなかった。だが今は、ひどく臆病な気持ちになった。
「インチョーくんのこと、前のクラスでよく話になってたのよ」
「……なんで?」
「すごく無口で、でもとっても頭が良いって。ほんとにそうみたいね」
普段の数十倍の時間をかけて、言葉が脳に入ってくるようだった。
(頭がいい? いったいなんの……)
ああ、誰かがそう言ってたのかと思いあたると、なぜかまた嬉しさがこみあげて、顔面がゆるみかけた。鏡をみたら、こぶとりじいさんみたいに、垂れさがってるんじゃないかと思った。
「……おれは別に頭がいいわけじゃない。だれから聞いたか知らないけど、そいつは嘘つきだ。ほんとに頭が良いのはハカセだよ」
インチョーは、どうしてかぶっきらぼうな口調になってしまうことに違和感を覚えながら、ぶあつい黒縁メガネをふいているハカセを、目でしめした。

女の子がハカセを見てから、インチョーを見ると、ニコリとした。
その笑顔に(おい、マウス。間違ってるぞ)とインチョーは思った。
(足し算じゃない。かけ算だ)
カワイイ、かける、笑顔は、ものすごくカワイイだ。
「ハカセくんのことも知ってるわ。去年、おなじクラスだったもの。天才ってみんな言ってるし。インチョーくんのことっていうより、あなたたちのグループ全員を知ってるっていったほうがいいのかな。インチョーくんが、前の六年の人たちとケンカしたこととか、行方不明の子のニュースとか、探検とか、色々有名よ」
笑いながら話す女の子は、誰かに似ていた。
たとえば本の中のお姫様だ。
『シンデレラ』、『不思議の国のアリス』、それとも『親指姫』か。
いや、もっと活発だ。『風の谷のナウシカ』とか。
いったい誰に似ているんだろうとインチョーは考えた。

「なんていうか、ハカセくんみたいな頭の良さじゃなくて、インチョーくんには違った頭の良さがあるって言うか」女の子が言った。「そうだ、わたしの名前しってる?」
(しまった! くそ! あのとき、ちゃんと聞いとけばよかった!)
「……ごめん、知らない」
「そうなんだ」女の子が残念そうに言った。「わたし、小町光。こまちってみんなに呼ばれてるけど、好きに呼んでいいから」
「……わかった」
小町光、小町光、その名前が頭の中を埋めつくした。
話せば話すほど頭の中に霧がかかるようで、インチョーはあいづちをうつだけで精一杯だった。
だが、なぜか嬉しさはとめどなくあふれつづけ、まったくおさまらない。
席替えが終わり、班長決めになった。
インチョーの班では全員が一致して、有無を言わさずインチョーが班長に選ばれた。
班の紹介やら目標やらをみんなと相談するあいだも、それを光が書いていくあいだも、インチョーは光をちらちらと見ていた。
見すぎているとは、気づけなかった。

ほっそりした指がマジックを持ち、紙に文字が生まれていくのを見ていると、赤ん坊が初めて立ったのを見るときのような、癒された心地になった。
何でも無い日常のひとつひとつが、小町光をとおすと、まったく別の新鮮なものに変わる。
(そうか、席替えって楽しいんだな)
みんなが大騒ぎする気持ちを、インチョーは、はじめて理解できた。
『学園天国』という歌がいっとき流行ったが、席替えが近づくとみんながそれを歌う意味もわかった。
たしかに勉強する気になる。それに、男子みんながライバルに見える。
(二学期も三学期も、隣になれるといいな)と思った。
鼻くそほじり名人、夏菜子の隣を射止めたのはマウスだった。
長治と喜びあったのもつかの間、マウスはゲロを踏んづけたような顔をしていた。
・目次 「六年生のあゆみ」