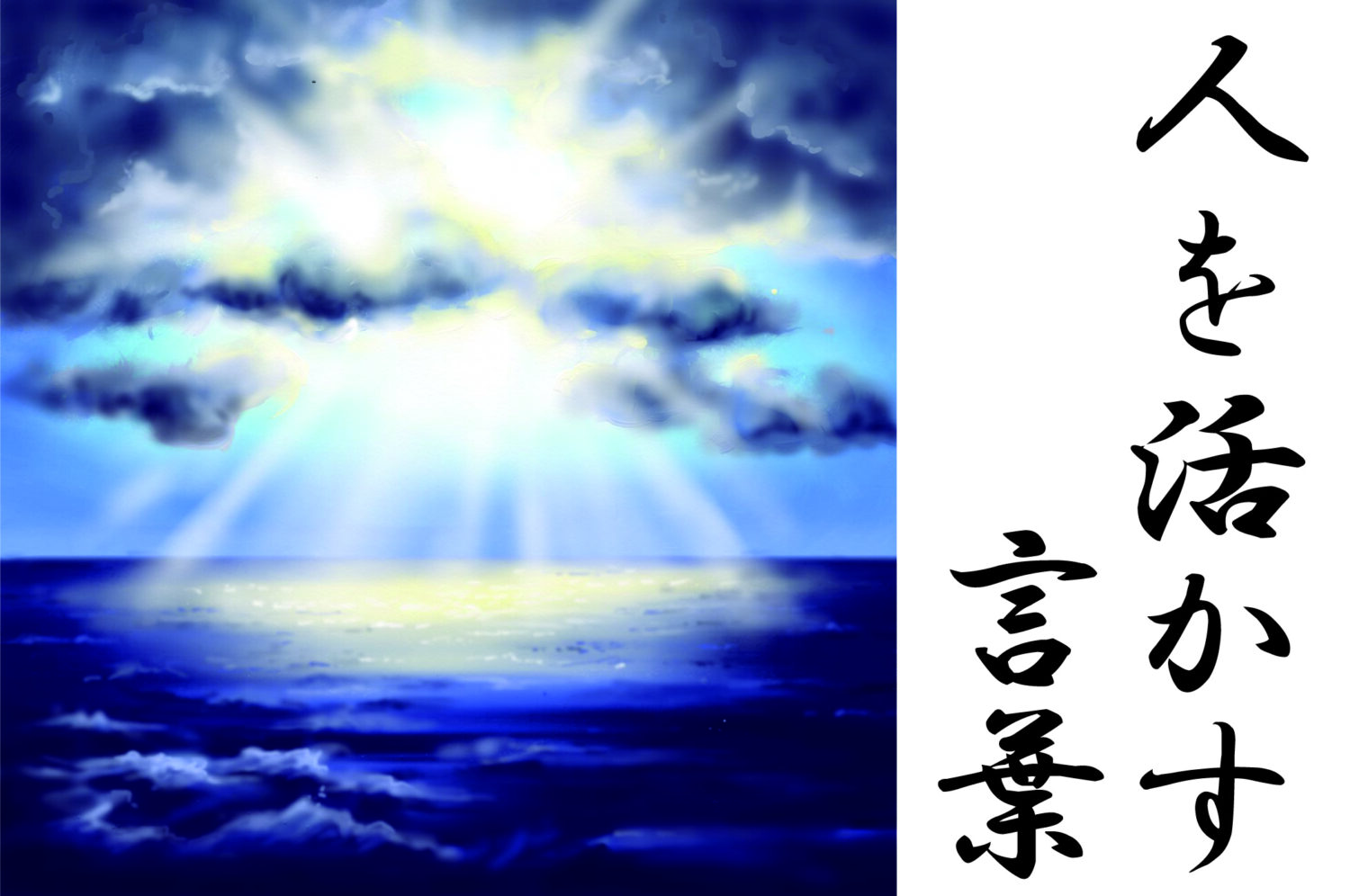少年と怪物
四月
母2 〜確認のため〜
平和な一日が崩れたのは一体何がいけなかったのかと考えながら、成子は車を海漁署駐車場へ車を乗り入れた。
スズキのエスクードは、夫の強い希望で買ったものだが、小さなジープとでもいうようで車幅がつかみにくく、二度切り返す羽目になり、成子は漁師町ならではの悪態をついた。

車のドアを音高く閉めると、警察署のガラス扉へ走るように歩く。
電話口で、本間という警察官から江利の名前がでた瞬間から、大人然とした心構えなど吹っ飛んでいた。
警察のお願いをすませたら、江利を何としても見つけると決めた。
過保護だといわれてもかまわない。
警察へ来る前に、とうとう夫にも電話をいれた。
米の配達中だった夫は、仕事中の電話に、あからさまに不機嫌な口ぶりだった。
江利が帰ってこないこと、遅くなるかもしれないから夕飯は食卓の上の物を温めて食べて欲しいと早口で伝えた。
夫に『年頃の女の子だ。そういうことがあるもんさ。君も覚えがあるだろう。今日は消防の集まりだ。飯はいらない』そう知ったかぶりで言われると、はらわたが煮えくり返った。
だがそれさえもどうでもいい。
夫は、江利と違って無事なのだから。
海漁署は三階建ての真四角で、窓が少なかった。
白い壁面がくすんでいる。
警察署というのは、悪いこともしてないのに、どうしてこう気遅れさせられるのだろうか。
警察署の前は海道で、挟んだ先に松の防砂林が広がり、その向こうに砂浜が見える。
九十九里海岸の南端である。

成子は入り口の扉に手をかけ、ためらった。
本間という刑事は口を濁し、電話では何も言わなかった。
とにかく来て欲しいということだった。
来て、確認して欲しいと。
江利が帰ってきたらこっぴどく叱ってやろうと、成子は決めた。こんなに心配させたのだから。
なぜか今朝、電子レンジで作った目玉焼きを、思いきり嫌な顔で食べていた江利の顔が目に浮かんだ。
(明日からは、フライパンに油をひいて作ってあげよう)そう思った。
二本の太い円柱が蒲鉾型の天井を支えている入り口をくぐる。
右手の掲示板に、敬礼する魚のおまわりさんのポスターがあった。
制服姿の魚が『守ります。海漁の平和と自然』と話している。
中は閑散としていて、カウンターの向こうで五人ほどの署員が立ち働いていた。
成子は、町役場と違って見当のつかない案内表示ばかりの窓口から、それらしいものを選ぶと、中年の女性署員に話しかけた。
「すみません。本間さんという方を呼んで欲しいのですが」
「どういったご用件でしょうか」
髪をひっつめすぎて、細い目が吊りあがっている女は、書類に何か書いていて顔をあげなかった。
成子は思わず声を荒げそうになったのをおさえながら、事情をかいつまんで説明した。
「ああ、そうですか。それじゃあ適当な席に座ってお待ちください」
成子は、奥にある自販機横のソファに座った。
一見、おだやかそうに見えるお婆さんが窓口の若い職員に食ってかかっていた。
漏れ聞こえる内容からすると財布を落としたらしい。
老女は、諸悪の根源は目の前の警察官であるとでも言うように睨みつけ、神経質にカウンターを叩いていた。
こういう輩が訪れるのだから、受付の女性のそっけなさも仕方ないのかもしれないと思った。
いちいちまともにとりあっては仕事にならない。
旅行に出かけるのでしばらく猫を預かってくれないかという電話が警察にくるご時勢だ。
署内は整然としていて、秩序正しく、落ち着きそのものだった。
しばらく座っていると、騒ぎすぎなのではと不安になってきた。
この田舎で子どもが行方知れずになるなど、ありえないことだ。
二重になった奥の扉から五十歳前後と見える男がやってきた。
頭髪がかなり薄く、太鼓腹だ。
「相原成子さんですか」男が言った。
成子はうなずいた。
「わざわざきてくださり、ありがとうございます。本間です」
刑事の口調はなまりが強かった。そして普段はもっとぶっきらぼうな話し方だろうと思った。
「右手、どうかされましたか? 腫れてるようですね」
「何かにかぶれたんだと思います。でも平気です。痛くもないですし。それより早く用事を済ませたいんですが」
「ああ、すいません。お忙しいのに質問してしまって。商売柄、クセでして。地下へ行きましょう」
地下と聞き、遠のきかけていた嫌な予感が強烈にぶり返した。
成子は刑事の後へついていった。
「あの、何をするんでしょうか」
「任意なので、嫌であればやめていただいても結構です。ただ私は相原さんに確認してもらうのが一番じゃないかと思いまして」
「何を確認するんですか」
「言いにくいことですが……手、です」
「何ですって」成子は立ち止まった。
「手です」
刑事が振り返った。冗談を言っている目ではなかった。それどころか恐ろしく真剣だった。
「人間の右手。それも子どものものです。奥さんに通報していただいた現場のすぐ近くで発見しました。爪も他に何枚か」
タチの悪い冗談だと思いたかったが、裏腹にひどい目眩がした。
「相原さん、大丈夫ですか」本間刑事が言った。「見る時は私が横についています。それから部屋の外にも一人います。もちろん扉は開けたままで。気分が悪くなったらすぐに外に出られます。何も心配はいりません。損傷のひどい部分は布で隠してありますので、綺麗な部分だけを見ていただくかたちです」
刑事が、自分をとても気遣ってくれているのがわかり、それがまた成子をひどく不安にさせた。
(なぜわたしがそんなものを見なければならないのだろう)と。
「どうしても見ないといけませんか」
「できれば」本間刑事が強いまなざしで言った。
「……わかりました」
はやく終わらせて、さっさと江利をみつけにいこう。
それでまた、今朝までの平和な時に戻れるのだから。今では完璧そのものだと思える、幸せなときに。
・六年生のあゆみ 目次