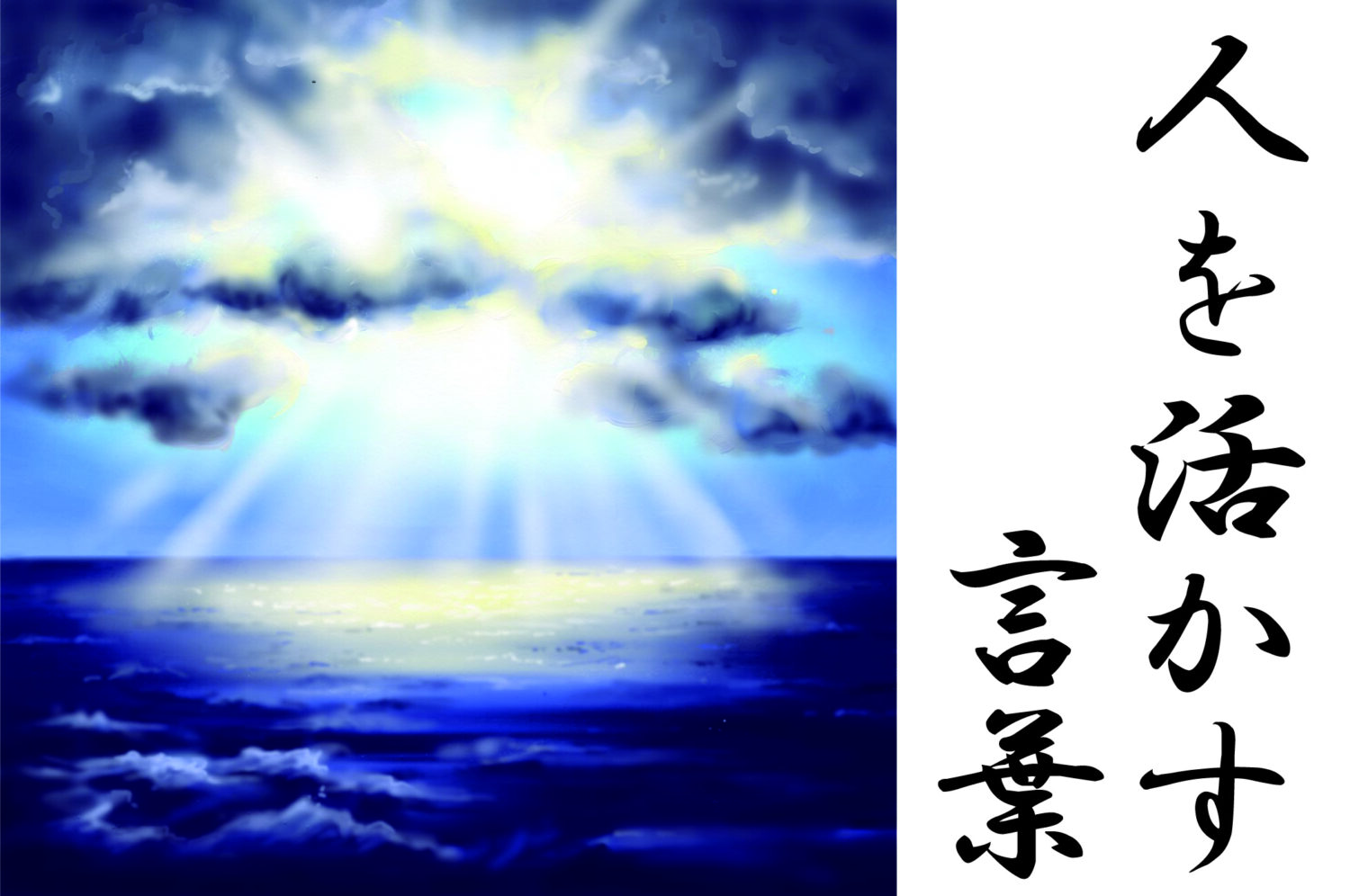少年と怪物
四月
茶ん爺4 〜港町〜

自転車のスピードをおとして、米仲港にのりいれた。
堤防のわきにチャレンジャーをとめる。
スタンドを立てると、チャレンジャーがキシッと音を立てて、また眠りについた。
あぶない走り方をするほど、チャレンジャーは目をさます。よろこぶように。
なぜだろうか。まるであぶないことのわからない子どもみたいだ。

堤防に立つと、太平洋が一望できた。
港には、三十人が雑魚寝できるトタン屋根の漁師小屋が、ふたつならんでいる。灰色の三角屋根が、太陽の光でにぶく光っていた。
茶ん爺の小屋はそこにない。
その性格とおなじで、孤独が好きだ。古い小屋は、港の、突きでた先端に建っている。
インチョーは港をながめながら、両腕でバランスをとりながら、堤防の上を歩いた。
昼の海は静かだった。ちゃぷん、ちゃぷんと、ちいさな波が堤防のコンクリートにあたっている音だけだ。
カタカナのコの字型をした港には、三十ほどの漁船が係留されている。

『なぜ港は、コの字型をしているの』と、茶ん爺にきいたことがあった。
『ああ? 入り口が海にむかって空えてれば、もろに波がへえってきてしまうからに決まってらぁ。だかん、コの空えたとこが、海にてえして横をむいてっだろ。そいに、コだとすりゃあ、上が倍も長え。だから湾の中ぁ、もっと静かになんだ』
『いろいろな工夫がされてるんだね』インチョー はこたえた。
なまりが強くて、半分かた、わからない。
でも意味はわかるので、不都合はなかった。
『へっ。あったりめえのことだろ』
すべての船が岸壁のそばに浮いているのではなく、五隻ほどは、傾斜のきつい入水口に陸揚げしてある。
それらは、すべて廃船だ。海の上をはしることは、二度とない。
坂の一番上に、巻き上げ用の強力なウインチをおさめた小屋がある。
台風の前日、インチョーは船の陸あげを手伝ったこともあった。
『泣き虫坊ん主! 手ぇ、挟むなお! 何人も片腕になっとっからよ!』
昔はこうしたウインチがなかったから、人力でひっぱりあげたらしい。
『そんどころでねえど。昔ゃ、船もよお、モーターもエンジンもねくて、手漕ぎだったんだ』
海は透きとおらない青、風はべたなぎだった。
潮の香りに、うちあげられた海藻の、腐るにおいがまじっている。
海面で何かがはねた。一瞬だけ銀色の腹が光り、水しぶきがあがった。
波打ちぎわのすべるコケを、二羽のカモメがせわしなくつついている。
ベラの群れはしょっちゅう、いっせいにむきをかえて泳いでいた。

(ああ、みんな生きてる)
インチョーは、あたりまえのことを思った。
(死にそうなのは、おれだけだ)
インチョーはあたりまえでないことを思った。
太い竹を組んだ物干し竿が、林のように百ちかくも並んでいる中を、ジグザグにとおった。
物干しには、伊勢海老用の、青や銀色や赤など、色とりどりの網や、漁師たちのシャツやタオルもかけてあって、インチョーがそばをとおると、ほんのすこしだけ、なびいた。
ななめにならべた網戸には海草が干してある。
真冬なら十枚で五千円もする高級な幅海苔、二月〜三月の春先なら鹿尾菜などが干されるが、この時期は若布だ。
小蝿がたくさんたかっている。もっとも、四月のワカメはまだ固いので、食べるのは物好きといわれるらしい。
漁師小屋から二人の漁師がでてきた。
インチョーを見るなり、ふたりともにっこりした。
漁師の笑顔というやつは、どうしてか、普通の職業のそれより、数段上におもえる。
「おう! 級長さん! 学校は終めえか?」クマというというあだ名の漁師が言って、
「勉強の具合はどうだ!」
吉次郎をちぢめて、キチという漁師が鉛筆で書くまねをした。
ふたりとも、怒ったような声のおおきさだが、これがふつうだ。
なんでも、海の上で風や波の音に負けないように声を出しているうちに、こうなってしまうらしい。
「はい。まあまあです」
「おお、級長さんは頭がいいかんなぁ。今日も爺んとこか? おめえは変わったやろうだあな」
クマさんが言った。クマさんは、米中港で二番目に腕がいい漁師だ。
「なぐられっなよ」
キチがげんこつをおとすまねをした。
「いえ、おれは変わってません。ふつうだとおもいます。はい。なぐられないように気をつけます」
「今年は暑うなりそうだど。帽子でもかぶれや」
クマさんが、かぶっていた麦わら帽子をさしだした。
「ありがとうございます。でもだいじょうぶです」
インチョーは頭をさげた。

茶ん爺の小屋は、なんの木で造られているのかもわからないほど古く、くすんで、黒一色だ。入り口はせまくて、全体の雰囲気は仏壇そっくりだ。
小屋の前に、茶ん爺のライトバンが停めてあった。これまた古い。持ち主も建物も車も、なにもかもが古い。
「茶ん爺。こんにちは。入っていい?」
インチョーは外から声をかけた。
「おう。へえれさ」
なかからしゃがれた、太い声がした。
竹の暖簾をよけ、なんでこんなに高いのかという桟をまたぐ。
窓はあるが、電灯はない。中は暗かった。
窓はすべてあけはなたれていて、空気が流れており、心地よかった。
床の半分は地面から板であげてある。そこに、けばだった畳が二枚しかれている。
茶色い丸座布団に、米仲港の主がどっかと座っていた。《網元》という漁師の元締めだけがこの小屋を使える。
茶ん爺は、手の平ほどある巨大な釣り針に、透明な天蚕糸をつけていた。
『爺は鯨でも釣る気かいや?』と、漁師仲間が陰であきれ混じりにいう、いつものだ。
「おう。ひさしぶりだあな。この泣き虫坊ん主が」
茶ん爺が白い歯をみせた。
〜「茶ん爺5 〜サメっこが人を食う理由〜」へつづく〜
・目次『六年生のあゆみ』