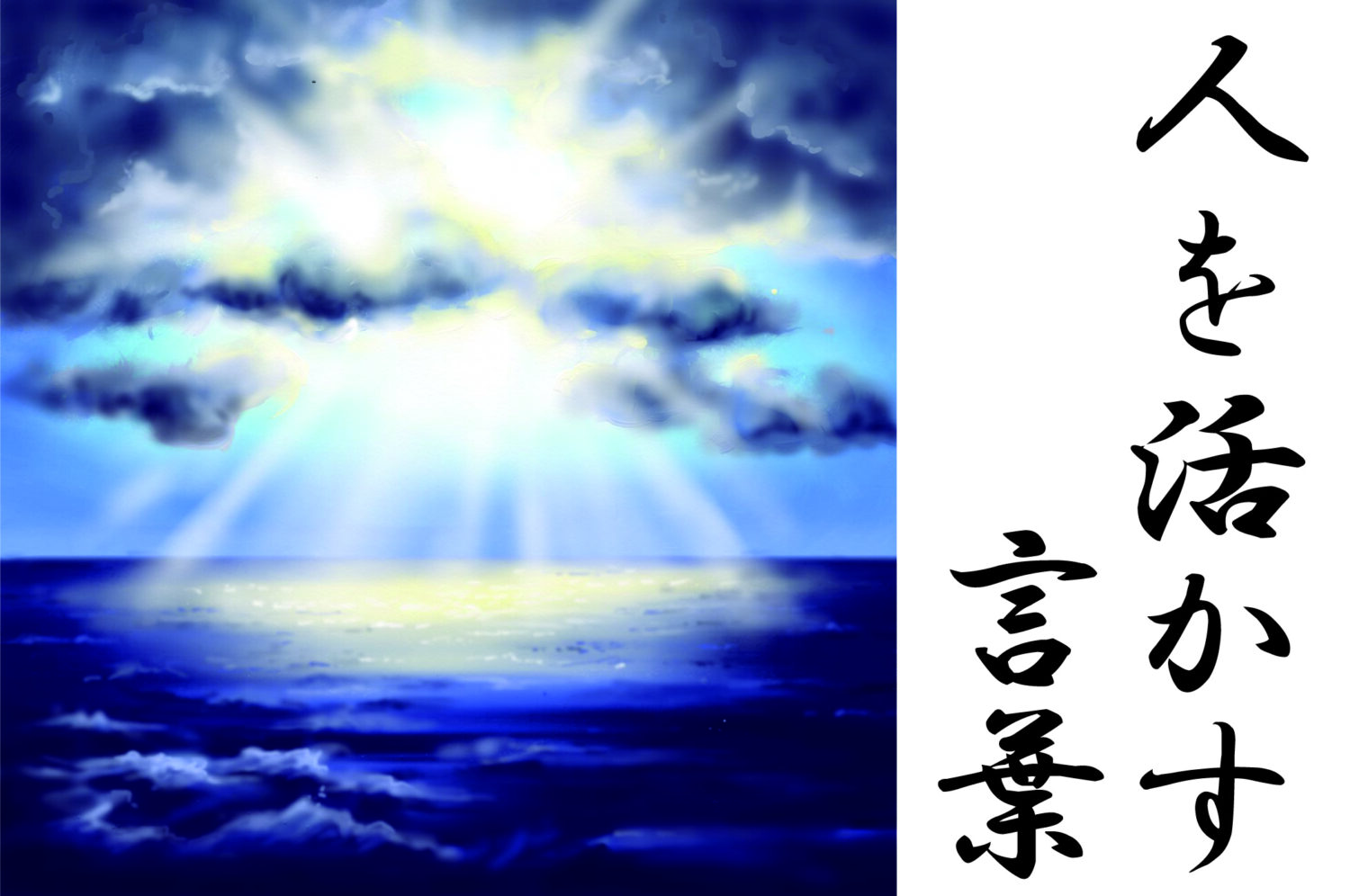少年と怪物
四月
異変2 〜 虫 〜
【駐車場 外吉】
外吉はタバコに火をつけた。
一本目を一気に吸い、次の一本になってようやくゆっくりと煙を吐き出す。
大量の煙を鼻の穴から青空に吹きだし、いらだちがすこし鳴りを潜めたころには、足下に燃えさしが五つ並んだ。

六本めを踏みにじりながら七本目をくわえると、ようやく体の奥から、いつものあの、なんでもできるという自信がみなぎってきた。
外吉は鼻を鳴らした。
「そうとも。俺様はなんでもできる。ガキどもなんぞに負けやしねえ」
「ナメられやしねえんだ」
「あいつらより小せえ頃から、俺ゃあ火かきで気絶するほどぶん殴られて、畑を耕してたんだ。いまどきの甘ったれた、なよガキどもの鼻っ柱をへし折るくれえわけねえ」
「いまどきの学なんぞクソの役にも立たねえしな。ほんとに頭がええっちゅうのは、学校の勉強なんぞとは違うんだ」
「そうとも、ぴいぴいのひよっ子どもが百人集まったって、俺様にかなうもんか。ガキどもめ、だしぬこうったってそうはいかねえぞ。てめえらは、外吉様には絶対にかないっこねえんだ」
外吉は早口で喋ると、ニコチンで黄色くなった歯をむきだし、にやにやと笑った。北口の便所へと歩いた。
「うんうん。そうともそうとも。あのガキにゃ、たっぷりとお仕置きしてやらにゃいかん。それが大人の務めってもんだ。とびっきりのきつい正しさをぶちかましてやるのが、優しさってやつだ。父なにしろ親がいなくて、世界がテメエのモンだと勘違いしちまった、ひん曲がった根性だからな。そうだ、それがええ」
便所の白いコンクリートの壁の手前に、汚水をくみだすマンホールの蓋が四つ並んでいる。そのまわりに虫がいた。
つまんで放ってやると、子どもが死にそうな悲鳴をあげる愉快な虫、百足だ。
三十センチほどで、なぜか驚くほどの数がいた。そう、百匹はいる。
よくみれば雑草のあいだにも、無数に蠢いていた。

「なんだ?」
ムカデは暗がりを好む。陽の光の下で見ることは滅多にない。
ムカデたちは、その名のとおり、百本の針をつけたような体で、激しく攻撃しあっていた。
節のある黒い胴で相手に巻きつき、強力な顎で噛みあっている。
小さなムカデたちはすでに死んで、丸まっていた。子どものようだった。
さらに奇妙なことがあって、ムカデたちの固く黒い殻が、何やら丸く膨れている。透明な水いぼといえば良いだろうか。小さな水風船をいくつも体につけている。
どのような生き物においても、共食いや子殺しは滅多に起きない。外吉もそれは知っていた。太平洋戦争の末期に、飢えた母犬が子犬を食うのを見たことがあるが、それくらいだ。
共食いは種族保存の法則に、子殺しは自己保存の法則に反する。
「何だってんだ。気味がわりいな」
外吉は辺りを歩き、植えこみの中にも奇妙なものを見つけた。
五つの葉っぱが星形を作る五加の木に、少々季節はずれのクモの巣が張っていた。
巣の中心に、黄色と黒の縞模様の大きな黄金蜘蛛が足を広げている。
黄金グモは、もうすこし暖かくなってから出てくるはずだった。

だが奇妙なのは、それではない。
巣に、白い糸にくるまれた獲物が垂れ下がっている。
ハエやブヨなど、小型の羽虫だ。
死んでいるのではなく麻痺毒を打ちこまれて、保存食になっている。
それらの食料にまじって、おびただしい数の子グモが、繭にされてぶら下がっていた。
子グモは土の上にも散らばっており、腹を見せて死んでいる。
母グモは、破れそうなほど獲物でいっぱいの巣で、じっと動かない。
そして母グモの背中には、ムカデと同じ水いぼができていた。
マダラ模様が膨れて薄くなり、水疱は今にも破裂しそうだ。
その内部は、白い液体で濁っていた。
外吉は、竹ぼうきで払いとばし、ムカデもクモもひと所に集めると、それらをすべて焼いた。
「初恋 〜 運命の席替え 〜」につづく
・目次 六年生のあゆみ