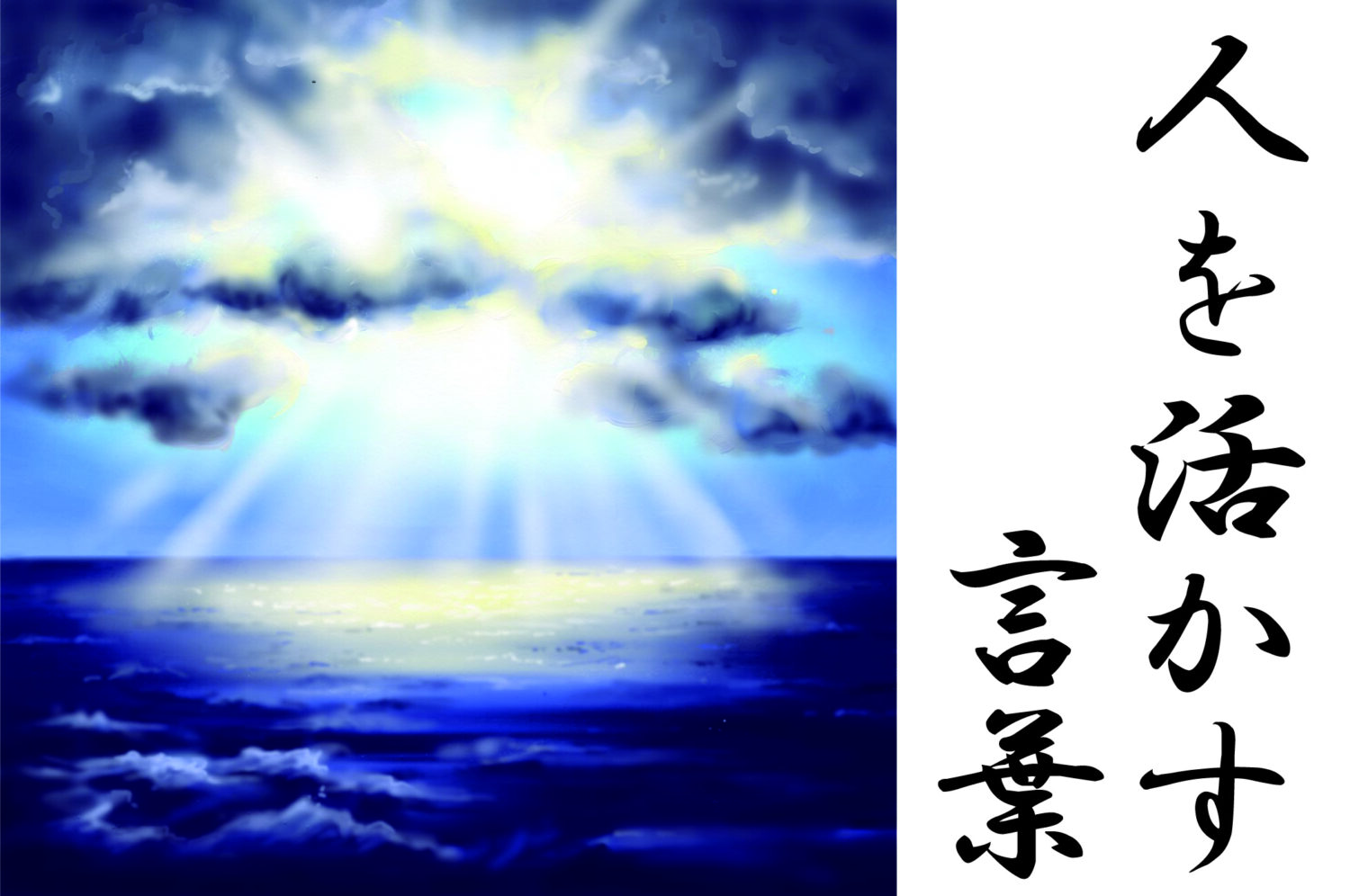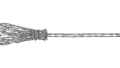少年と怪物
四月
小学校1 〜だれしもの記憶〜
【四月七日 七時十分 インチョー 自室】
(六年生はどんな年になるだろうか)
インチョーはランドセルと手提げバッグに荷物を入れていった。
青いゴム革の上履き。
古いパジャマの生地を使った防災頭巾(使って六年目をむかえる母の手製)。
十六色のぺんてる絵の具。
クリーム色の筆洗いバケツ。
硯、毛筆、文鎮など書道道具一式。
そのほかこまごまとしたもの。
ランドセルには筆箱とノートだけだ。だが今日新しい教科書が配られるので、ぐっと重くなること間違いなしだ。
支度をしていると、なぜか胸の奥がふわふわしてきて、自然と口の端が持ちあがった。
両手いっぱいの荷物を並べ終わると、黒地に赤のラインが入ったジャージに着替え、居間にもどった。
小さな卓袱台で、一人分の食事が湯気を立てている。母親は土間に腰かけ、靴を履いていた。土間といっても靴を五足も置けば埋まるほど狭い(もっとも、自分と母さんで合わせて五足も持っていない)。
母の横には、大きな黒いゴミ袋が置いてあった。
「食べ終わったら水に冷やしておけばいいから」母が靴ひもを結びながら言った。
「洗っておくよ」インチョーは座った。
振り返った母の眉間に、深いたて皺が寄っていた。
「あんたは良くできた子よ。頭の回転も悪くない。でもまだ子どもなの。子どもは母親の言う事を聞くものよ。わかった?」
「いただきます」インチョーは熱いみそ汁をすすった。
「まったく。ほんとに頑固ね」
母がため息をついた。
「あたしの手があんたのほっぺたを引っぱたきたくてうずうずしてるって知らないの? いったい誰に似たんだか」
「いってらっしゃい」
母さんは目を細めただけだった。
母さんがその先を口にすることは絶対にない。息子がいったい誰に似たのか。
インチョーも聞きはしない。
「いってくるわ。帰りはいつもの時間になるから先に夕飯を食べて、お風呂に入っておいて。何かあったら遠慮なく電話しなさい」
「いってらっしゃい」インチョーは言った。
母が大げさに肩をすくめ、ゴミ袋をひっつかむと、たてつけの悪い引き戸に、そのうち叩き割って燃やしてやると悪態をついて蹴飛ばし、出ていった。
湯気の立つ白飯、刻んだ海苔をまぶした納豆、はじが焦げてカリカリになった目玉焼き、ほうれん草のみそ汁。
朝食を食べ終えると、「ごちそうさまでした」とインチョーは手を合わせ、母の食器も、鍋やまな板、包丁も洗った。
歯を磨き、家を出た。鍵はかけない。網船区のほとんどの家がそうだ。
それに、そもそもウチには盗まれるような高価な物など無かった。
あまりに何も無くて、かわいそうに思った泥棒が何か置いていくわと、いつか母さんが冗談を言っていた。
曲がりくねった田んぼの畦道を、カエルの合唱につつまれて歩く。車前草や風草が露に濡れていて、靴にたくさんの水滴がついた。

県道に出た。車は一台も通っていない。
こんもりとした角砂森に目を細めた。涼やへ、雀の群が一斉に飛び立った。
(あの時は大変だったな。新聞に載るなんて思わなかった)
一年前になるが、小さな男の子が角砂森に遊びに行き、行方不明になった。
数日のあいだ見つからないその子を見つけたのは、インチョーら〔失われた世界〕のメンバーだった。
六年生でもまたあんな事があればいいとインチョーは思った。
いや、次はみんなでもっとでかいことをやるのだ。
集団登校の集合場所である用水池につくと、五年生の丸山舞、その弟で四年生の丸山聡志がいた。

舞はまったく表情が無く、赤いランドセルの肩紐を握ったまま、宙の一点を見たまま動かない。
聡志は奇声をあげて、地面に落ちている物を手当たりしだい拾っては、用水池に投げていた。手近に何も無くなると、木の枝を折って、投げる。
ふたりとも、いつもどおりだった。
インチョーはこの姉弟が苦手だった。
やることがすこしばかり妙というのもあるが、単にお金持ちの家の子だからだ。
着ている服も靴も上等で、何かこう彼らの前にいるだけで恥ずかしい気にさせられる。
しかし毎晩夜になると、丸山家から、このふたりが何か拷問でも受けているような悲鳴をあげることを誰もが知っている。
腕や足、ときには顔に大きなアザを作っていることも多い。
だからインチョーは、誰かに怪我をさせるようなことがないかぎり、このふたりは好きにさせておくようにしていた。
ほどなくして、右目から頬に地図みたいな大きな青アザがある三年のバチョフ拓馬(このあだ名はソ連の大統領のゴルバチョフを縮めたもの)が眠そうに目をこすりながらやってきた。
畳屋の長女で、スイカの種ようにたくさんホクロのある五年の由実、その妹で一年の真里の遠藤姉妹も、いつものようにケンカしながらやってきた。
千葉県中部の君津市の鉄鋼会社で働く父をもつ四年の井口孝介は、発売したばかりのゲームボーイを持ってやってきた。
「学校に着く前にしまえよ」インチョーは三百回をこすほど繰り返している言葉を言った。
「あったりきです」孝介が言った。
通学中でも学校でも、ゲームなどをしたら誰かにチクられ、先生に殴られ、取りあげられる。
だから孝介はそれの電源を入れることはないし、校門の前でランドセルにしまう。
お守りのようなものだとインチョーは思っていたが、やはりクラスでは自慢野郎と呼ばれているそうだ。
もう七人がやってきて、顔ぶれがそろった。
インチョーが班長をつとめる登校班・第六班は小学校へと向かった。
通学路は迷路道と呼ばれていた。
右へ直角に折れたと思うと一、二歩ですぐ左へ、家の庭に入ると見えた先に道があり、自転車がすれ違えないほど狭いブロック塀のあいだを抜け、急すぎる坂道に出て登り、くだる。
地元民でなければ確実に迷う道で、実際、都会からきた車が、前にも後ろにも行けなくなって立ち往生していることもある。
昔、迷路道で子どもがよく神隠しにあったと、お年寄りたちは口にしている。
何か恐ろしいものがいて、子どもをさらって、食ってしまうと。
夕方になると不気味で、物陰に妖怪がいそうな、またはそのまま異界に入ってしまうような、そんな道だ。
神隠しに遭ったという子で、ただ一人、なぜかシュウという男の子の名前だけ伝わっている。
なぜその子だけなのか、インチョーは理由を知らなかった。この時は。
邪悪なものたちの棲家であるように、迷路道にもまたさまざまな場所に防空壕があって、真っ黒い口をあけていた。

インチョーはついてきていない子がいないか、振り返りながら気を配りつつ、防空壕の一つ一つにちらりと目をやり、「あれはやった」、「あれはやってない」と、確認しながら歩いた。
みなが新学期の始まりにふさわしく、だれとおなじクラスになりたいとか、新しい先生はだれかなどと、はしゃいでいた。
それでもインチョーに話しかけるものは誰もいない。
最上級生だからではない。
相手をじっと見つめて話を聞くこと、ひどく無口なことで不気味だと思われているからだ。
しかしインチョーの方も、とくに話したいとは思わなかった。
話す相手はメンバーだけで十分たりていた。
「小学校2 〜男の子の幽霊と用務員〜」につづく
・目次 「六年生のあゆみ」